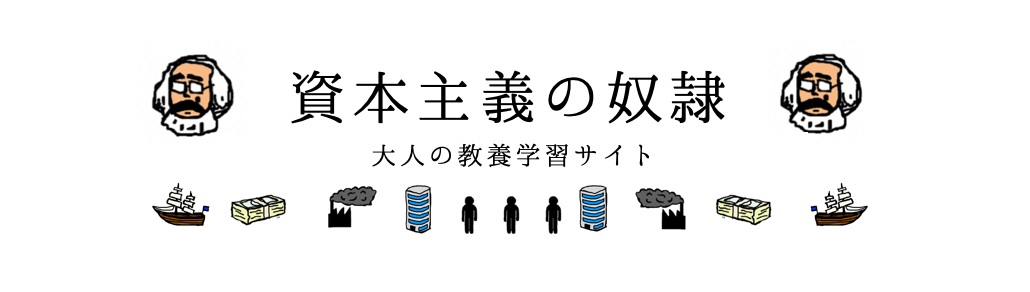この記事では、仮想通貨で時価総額2位となっているイーサリアム(ETH)の特徴や将来性、歴史とマージについてわかりやすく解説します。
また、この記事ではイーサリアムとは
- ヴィタリック・ブテリン氏によって2013年に考案されたプラットフォーム
- スマートコントラクトによって契約を自動化する仕組みを導入
- イーサリアムからは、DeFiやNFT関連のサービスが構築されている
そこでこの記事は、プラットフォームとしてのイーサリアムについて通貨としてのイーサもあわせて解説していきます。

この記事は、経済オタクで仮想通貨にハマっている労働者マンが解説します
- イーサリアム(ETH)についての理解が深まる
- 仮想通貨(暗号資産)の投資を始める上で知るべき基礎知識が身に付く
イーサリアムとは

イーサリアムとは?
イーサリアムとは、2015年に正式ローンチされた世界最大級の暗号プラットフォームの名称です。
2022年現在に至るまでに、イーサリアムは仮想通貨時価総額ランキングで長きに渡って2位の地位を維持しています。

イーサリアムは、仮想通貨の名称と誤解されることがありますが、あくまで様々な仮想通貨関連のサービスを構築できるプラットフォームの名称です。

このプラットフォームの基軸通貨として機能しているのが、ETHになります。
- 様々な仮想通貨関連のサービスを構築できるプラットフォームの名称です。
- イーサリアムの基軸通貨として機能しているのがETH
運営主体イーサリアム財団と開発者ブテリン
イーサリアムは、2013年にヴィタリック・ブテリン氏(@VitalikButerin)によって考案されたものです。

主に、開発運営を行なっているのはイーサリアム財団(Ethereum Foundation)で、イーサリアムの技術的発展をサポートする非営利団体です。

ビットコインとイーサリアムの違い
イーサリアム(ETH)は、ビットコイン(BTC)と目的や用途が大きく違います。
ビットコインは、価値の交換や保存といった決済用途が目的です。
しかし、イーサリアムはプラットフォームとして利用されることが想定されています。そのため、イーサリアムからはdApps(分散型アプリケーション)によって様々なWebサービスを展開することができますい。

| 通貨単位 | ETH |
| 時価総額 | 2位 |
| 発行枚数上限 | なし |
| コンセンサスアルゴリズム | Pow(のちにPosに移行予定) |
| ホワイトペーパー | White Paper |
| 公式サイト | ethereum.org |
イーサリアムの特徴

イーサリアムからアプリケーションの開発が可能なプラットフォーム
イーサリアムはスマートコントラクトを実装しています。このスマートコントラクトによって、アプリケーションを展開することができます。例えば、dApps(分散型アプリケーション)や、DeFi(分散型アプリケーション)等が挙げられます。
dApps(分散型アプリケーション)とは何か知りたいかたは以下の記事もあわせてお読み下さい。
そのため、イーサリアムは、アプリケーションを展開するプラットフォームとしての機能があります。この機能はスマートコントラクトによって契約の自動化が可能になり、実現しました。

- チェーン上にdApps(分散型アプリケーション)の開発が可能に
- 契約内容が改ざん、契約の不履行を防止することが実現可能に
スマートコントラクトとは何か知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。
スマートコントラクトの登場
エコシステムが広がっている
イーサリアムがプラットフォームとして機能していることで、非常に広大なエコシステムが広がっています。イーサリアム上にdApps(分散型アプリケーション)や、DeFi(分散型金融)プロトコル、、DAO(分散型自律組織)、GameFi(ゲーミファイ)などが展開されています。

Proof of Work(PoW)からProof of Stake(PoS)
イーサリアムのコンセンサスアルゴリズムはマイニングによって通貨が発行される Proof of Work(PoW:プルーフ・オブ・ワーク)が採用されています。
PoWとは、取引の承認をマイニングという暗号解読作業をしたものの中で、一番早く解読作業を完了したものに報酬を与えるコンセンサスアルゴリズムです。

取引の承認をマイニングという暗号解読作業をしたものの中で、一番早く解読作業を完了したものに報酬を与えるコンセンサスアルゴリズム
今後、イーサリアムは2020年からイーサリアム2.0のアップデートを開始しています。
具体的には、マイナーの通貨保有量や保有期間を基準に、マイニングの難易度を調整する Proof of Stake(PoS:プルーフ・オブ・ステーク)へ移行を計画実行中です。

近年話題になっている、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)という分野においても、イーサリアムのブロックチェーンが利用されております。
- イーサリアムは、マイナーの通貨保有量や保有期間を基準に、マイニングの難易度を調整する Proof of Stake(PoS:プルーフ・オブ・ステーク)へ移行を計画中
- PoWはスケーラビリティ問題を引き起こしやすい
イーサリアムの発展

このように、2013年のイーサリアムの誕生から、2020年以降、DeFi(分散型金融)やNFT(非代替性トークン)が構築されるようになりました。
プラットフォームとしての特徴に持つイーサならではの出来事でした。そのため、広大なエコシステムが出来上がっています。

DeFi(分散型金融)
ちなみに、DeFi(分散型金融)とは、銀行や証券会社などの金融仲介業の存在を無効化して、ユーザー同士での取引を可能にするアプリケーションのことを指します。

これによりUniswapに代表されるDEX(分散型取引所)のような、中央管理者のいない取引所が生まれたのです。DeFiに関しては別の記事でも解説しているのであわせて読んでみてください。
また、イーサリアムベースで開発されているDeFiサービスには
のサービスがあります。

銀行や証券会社などの金融仲介業の存在を無効化して、ユーザー同士での取引を可能にするアプリケーション
NFT(非代替性トークン)
また、NFTとは非代替性トークンの略で、ネット上のデータを複製できない唯一無二なものであることを保証されたもののことを指します。
仮想通貨は代替性が高いですが、NFTは非代替的で唯一無二である点が特徴です。

また、イーサリアムベースでの有名なNFT関連のサービスには
- OpenSeaのようなNFT取引所があります。
- NFTに特化したレイヤー2プロトコルのImmutable X
があります。

非代替性トークンの略で、ネット上のデータを複製できない唯一無二なものであることを保証されたもののこと
DAO(分散型自律組織)
DAOとは、Decentralized Autonomous Organizationの略で、和訳すると分散型組織になります。管理者が存在せず、メンバーが共同所有を行うような組織のことを指します。

既存の組織のようなトップダウンではなく、究極の民主主義をテクノロジーで実現した(ようとしている)組織の形です。
イーサリアムの将来性

スケーラビリティ問題
イーサリアム(ETH)のデメリットとして、スケーラビリティ問題があります。スケーラビリティ問題とは、取引量の増大に伴いブロックチェーンが処理仕切れなる問題のことです。
これにより、取引手数料が高騰してしまう可能性もあります。

特に、イーサリアム上でのアプリケーションの増加に伴う取引の増大によってネットワークが混雑し、トランザクションの遅延が起きています。
- 取引量の増大に伴いブロックチェーンが処理仕切れなくなる問題
- 取引処理の遅延やガス代が高騰が起こってします
発行上限がない
ビットコインは発行上限が決まっており、マイニング報酬も半減期によって減っていきます。
しかし、イーサリアム(ETH)には発行上限がありません。発行上限がないイーサリアム(ETH)は、今後インフレを起こす可能性もあります。(インフレーションに関する記事はこちら)
イーサリアム(ETH)もマイニング報酬を減らし対策は行っています。ですが、今後発行上限が決められる可能性も少なからずあるでしょう。
必ず価値が下がるとは言えませんが、このまま枚数が増え続ければ、いつか問題になる時が来るかもしれません。
- 発行上限がないことでインフレを引き起こす可能性がある
ICO(新規通貨発行)への規制
イーサリアムではICOという資金調達手段が生まれています。
ただし、現在では世界的に「ICO規制」が行われています。2017年~2018年の仮想通貨バブル期には、各国でICOを利用した詐欺が大流行しました。
そのため、世界の国々において法規制がなされるようになりました。こうした法規制はイーサリアムが発展する上で大きな足枷となっています。
イーサリアムの歴史

イーサリアムは、 2014 年にブテリン氏が立ち上げたイーサリアム財団を中心に開発が進んでいます。
また、開発には4つのステージが明確に提示されています。
- フロンティア
- ホームステッド
- メトロポリス
- セレニティー
その方針を巡ってコミュニティー内では活発な議論が行われています。

イーサリアムの誕生前夜
イーサリアムは、2013年にヴィタリック・ブテリン氏(当時19歳!)によって考案されたものです。同年には、2013 年にブテリン氏はイーサリアムのホワイトペーパーを公表します。

さらに、2014年に開発資金を集めるため、イーサとビットコインを交換するプレセールを実行し、約 6,000万ETHが販売され、約 32,000 BTCを集めました。
その後、1年間の準備期間を経て本格的な開発がスタートしたのです。。
フロンティア(Frontier)
2015年7月30日、イーサリアムが一般公開されました。フロンティアは、いわばβ版であり開発者向けのアプリケーションでした。そのため、ミスが見つかっても修正できるようにしていたのです。
この頃からすでにイーサリアムのプラットフォーム上ではいくつかのプロジェクトが立ち上がりを見せています。

2016年3月14日、フロンティアから半年を経てイーサリアムが安定的に稼働することが確認されると、ホームステッドへのアップグレードが行われました。
ホームステッド(Homestead):DAO事件
ホームステッドへの移行が完了し、さまざまなプロジェクトが参入するようになってきます。その中でも注目されていたのが、THE DAOというプロジェクトです。
スマートコントラクトを利用して煩雑な事務手続きが不要なベンチャーファンドの立ち上げを目指したものです。
しかし、2016年6月にTHE DAOがハッキングされ、約50億円相当のイーサが盗まれるという事件が起こりました。これがDAO事件と呼ばれるものです。

この事態にイーサリアムのコミュニティは、被害者救済のためにハードフォークを行うことで対処しました。ハッカーが盗んだイーサの取引記録をブロックチェーンから削除し、被害者にイーサを返還するのです。
この時、ハードフォークに反対したグループはイーサリアムクラシックという新たな仮想通貨を運営するようになりました。

メトロポリス(Metropolis)
第三段階のメトロポリスは、2017年に行われたビザンティウムと、2019年に行われたコンスタンティノープルの2つのアップグレードから構成されています。

メトロポリスを通してイーサリアムは匿名性の向上、セキュリティーの強化、そして PoW から PoS への移行が計画される最終開発段階のセレニティーに向けた準備が始まりました。
イーサリアム2.0(セレニティ)
2020年頃からイーサリアム2.0、つまり最終段階のセレニティへの移行が完了しました。
イーサリアム2.0は、さらにの4段階で開発が進めらていました。
- フェーズ0
- フェーズ1
- フェーズ1.5
- フェーズ2
背景にはのちに解説するスケーラビリティ問題によるガス代の高騰があります。そのためには、コンセンサスアルゴリズムとPow(プルーフオブ)からPos(プルーフオブステーク)への移行が必要になります。

急激に変更するとトラブルが起こりかねないので、漸進的にプロジェクトが進められているのです。
2022年8月11日、イーサリアムがマージを完了しました。PoSへの移行に伴う段階のことを指します。
また、マージへにあたりCasperネットワークと呼ばれる技術を使用して移行を実施しました。

Casperネットワークに関しては以下の記事を参考にしてみてください。
PoS(プルーフオブステーク):保有(ステーク)する仮想通貨の割合に応じて、ブロックを新たに承認・生成する権利が得られるコンセンサスアルゴリズムのこと。
イーサリアムの価格動向とチャート

また、イーサリアムの価格は現在以下のチャートのような推移を辿っています。
参考までにご確認ください。
さいごに

また、この記事ではイーサリアムについて解説してきました。
- ヴィタリック・ブテリン氏によって2013年に考案されたプラットフォーム
- スマートコントラクトによって契約を自動化する仕組みを導入
- イーサリアムからは、DeFiやNFT関連のサービスが構築されている
イーサリアムを理解しないことには、現在のクリプト界隈の動向を理解することはできません。必ずイーサリアムに関しては、この記事に書いてある内容レベルは最低でも押さえておきましょう。