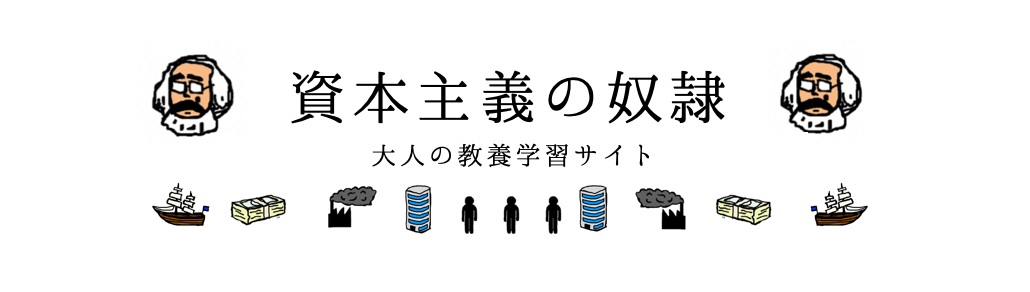ヘーゲルは、『精神現象学』で主張された弁証法やアウフヘーベン、『法の哲学』での市民社会論で有名なドイツの哲学者です。
彼は、カント哲学を批判的に継承し、絶対精神というあり方を主張しつつ、のちの近代以降の進歩論の主軸となりました。
そこで、この記事ではヘーゲルその人と、彼の思想が凝縮された『精神現象学』と『法の哲学』についてわかりやすく解説していきます。最後までお付き合いいただければと思います。
- ヘーゲルその人について知ることができる
- ヘーゲルの代表作である『精神現象学』と『法の哲学』について知ることができる
ヘーゲルの生涯

ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(1770年8月27日 – 1831年11月14日)は、ドイツの哲学者です。

1770年に、神聖ローマ帝国のでプロテスタント家庭の官吏の息子に生まれました。1788年にはチュービンゲン大学に入学しカント哲学や啓蒙思想にも触れています。ドイツ観念論のシェリングなどの親交を結びました。
1801年にはイエナ大学講師をしながら彼の主著となる『精神現象学』(1807年)を刊行しています。また、その頃プロセイン王国はナポレオンに敗北し、イエナ大学は閉鎖すると同時に教職を追われます。

しかしその時のナポレオンの姿を見たヘーゲルは「馬上の世界精神」と好意的に評価しています。その後、1816年にハイデルブルク大学の正教授職を手にいれ、1821年には『法の哲学』を執筆しています。

1829年にはハイデルブルク大学総長に選出されました。しかし、ヘーゲルは当時猛威を奮っていたコレラに倒れ、1831年11月14日に急逝しました。
ヘーゲルの思想:ドイツ観念論

ヘーゲルは、ドイツ観念論という哲学の潮流の中に位置付けられる哲学者です。ドイツ観念論は、カントの認識論を出発点に「自己意識」や「精神」、「自我」などの精神的なものについて理論を展開しました。

- カントの認識論を出発点に「自己意識」や「精神」、「自我」などの精神的なものについて理論を展開した哲学の潮流
カントは、物自体と認識、神と人間に分裂をもたらす理論を作り出しました。この分裂に対してフィヒテややシェリングは乗り越えを測ろうとしました。ヘーゲルも同様にカントの物自体と認識の断絶の乗り越えを図ろうとした人物です。
その乗り越えとして生み出されたのが弁証法的統合であり、それは『精神現象学』や『法の哲学』において前面に押し出されています。
ヘーゲルの『精神現象学』

全体は、「意識」「自己意識」「理性」「精神」「宗教」「絶対知」の6章からなります。ヘーゲルは弁証法というプロセスを通じて、原初の感覚的な意識から最高次の「絶対知」へと人の精神が進化していくプロセスを壮大なスケールで描きました。
ヘーゲル弁証法のアウフヘーベン
ヘーゲルの『精神現象学』の最も重要なキーワードとして弁証法的統合をあげています。弁証法的統合とは、簡単にいうと対立する物事から新しい見識を見いだす論理のことです。
弁証法とは、ある命題(テーゼ=正)と、それと矛盾する命題(アンチテーゼ=反対命題)という二つの対立したものが調停されアウフヘーベン(止揚)されます。その結果、より高次元の命題(ジンテーゼ=合)が生み出されるという考えです。

- 対立する物事から新しい見識を見いだす論理のこと
自己の登場と主観的精神
『精神現象学』では、ヘーゲルは「精神現象学」という新たな学問体系を打ち立てようとしました。その際に対象となるのが1人の個人としての主観的な意識についてです。具体的には、以下の三つのフェーズです。
- 感覚的な意識
- 自己意識
- 理性
まず、感覚的な意識が原初にあります。そこでは自己と他者の境界線が曖昧です。その後、知覚に至り、悟性にへと認識が登っていくことで、自己意識が芽生え出します。
さらに、自己意識を他者も持っていると知ることでさらに一つ上の段階へ認識が至ります。これを突き詰めると、自我を超えた「自己」を持つに至ります。これが、他者との共通性を持つ「理性」的な自己となるのです。

ここまでの、意識の弁証法的プロセスを深めるのが「精神現象学」としてヘーゲルは取り扱います。
個人を超えた客観的精神
「精神現象学」への言及は理性の段階まででした。しかし、『精神現象学』においてヘーゲルはさらに「客観的精神」、「絶対的精神」まで主張を広げます。

- 『精神現象学』では「精神現象学」という学問体系を整理した。ただ、学問としての「精神現象学」は主観的精神までが範囲内
まず、客観的精神では、精神や宗教について取り扱われます。「客観的精神」は主観的な精神から、絶対的精神に至るまでの中間地点のことを指します。
ここでは、主観的な1人の人間の範囲を超え、共同体レベルでの精神へと変わります。その背景には、ヘーゲルが生きた時代が、フランス革命による民主主義の登場があります。ここでは、法律や倫理、道徳など共同体のより具体的な人間社会のあり方について書かれています。

しかし、主観的精神から客観的精神へ至る中で、自然へと自己を対象化し(自己外化)、いったん自己と疎遠なものとなっていきます。
- 主観的な1人の人間の範囲を超え、共同体レベルでの精神のこと。法律や道徳、人倫がそれにあたる
絶対精神へ至る
この客観的精神と主観的精神という、一種共同体的なもの(客観的精神)と個人的なもの(主観的精神)が対立している状況から弁証法的統合をすることで至るのが絶対精神です。
絶対精神は、自然を否定して自己に帰るために、まず個人の主観的精神 (心・魂・意識)になってあらわれます。次に客観的な社会関係としての客観的精神(法・道徳・人倫)になり、最後に主観的精神と客観的精神を統一する絶対精神となって自己へ帰還するのです。

絶対精神は、存在と認識が一致して、カント流にいうならば物自体の世界に至った状態のことを指します。
- 共同体的なもの(客観的精神)と個人的なもの(主観的精神)が対立している状況から弁証法的統合をすることで至る状態
- 存在と認識が一致している究極の状態
ヘーゲルの『法の哲学』

『法の哲学』(1821)はヘーゲルの主著の一つで人倫について説かれた書籍です。これは、『精神現象学』の客観的精神にあたる部分に関する解説です。
客観的精神の三段階:抽象法-道徳性-人倫
客観的精神とは家族や市民社会、国家などの自由な人間の行為により生み出される精神が、具現化したもののことを指します。主に以下の三つの段階に区分され、その中で最終的に人倫というフェーズに達します。
- 抽象法
- 道徳性
- 人倫
人倫とは、人間の社会関係の抽象的な形式である客観的な“法”(抽象法)と、個人の主観的な確信にすぎない“道徳”とを止揚的に統一したものです。

人倫の三段階:家族-市民社会-国家
ヘーゲルは人倫もまた三段階に区分し、以下から成るものと捉えます。
- 家族
- 市民社会
- 国家
家族とは愛情や感覚という形式における主体(自分)と客体(他人)の統一の段階です。
ここに労働という体系に基づく市民社会が登場します。市場という欲望を原理に動くシステムの中で人々は労働という体系の中に組み込まれます。

次に、市場原理に基づく市民社会を包摂する国家が登場します。国家は、立法権や執行権、君主権を用いて人々の欲望に対して利己性を監視するようになります。
さいごに

彼は、カント哲学を批判的に継承し、絶対精神というあり方を主張しつつ、のちの近代以降の進歩論の主軸となりました。
この記事ではヘーゲルその人と、彼の思想が凝縮された『精神現象学』と『法の哲学』についてわかりやすく解説してきました。
彼の哲学は、進歩史観という、人間は常に進歩しているという価値観を生み出す始まりともいえます。ただ、近年の哲学では彼の哲学は批判され乗り越えられつつあります。
ただ、彼の哲学はいつまでも輝きを失うことなく、生き続けています。