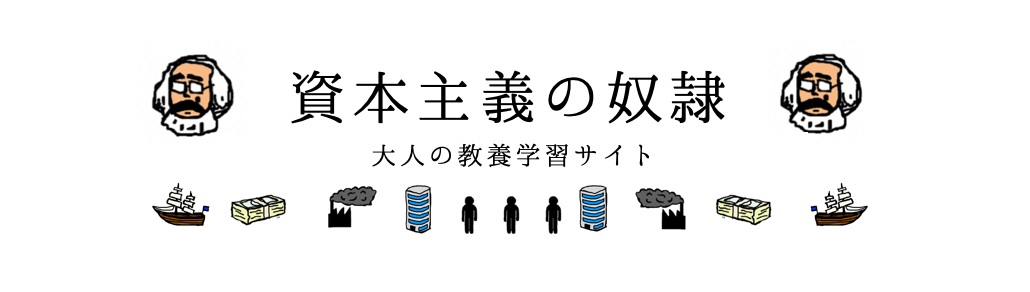この記事では、西洋哲学の流れについて解説していきます。アリストテレスやカント、ヘーゲルなど様々な哲学者が編み出して、作り出された西洋哲学についての全体像は非常に複雑です。
古代ギリシャ哲学からドイツ観念論にいたる近代哲学までざっくり解説していきます。この記事を読めば、西洋哲学の全体観を掴むことができます。ぜひ最後までお付き合い頂けると嬉しいです。
- ソクラテスから始まる西洋哲学の概要について理解することができる
- 西洋哲学の全体像を掴むことができる
西洋哲学の流れの概要

西洋哲学は主に以下のギリシャ哲学から近代哲学のドイツ観念論までの流れのことを指します。主に以下のような順番で哲学の潮流に変化が起きます。
- ギリシャ哲学:哲学の始まり
- 中世哲学:キリスト教と哲学の融和
- 近世哲学:理性優位とキリスト教の影響力の低下
- 近代哲学:神と哲学の分離へ
まず、最初にギリシャで哲学というものが生み出されます。それが中世になり、キリスト教と融合し始めます。
しかし、近世になると、理性が神学よりも優位に立つようになります。それは科学的な知識が普及し始めたことによります。しかし、未だ哲学と神学の繋がりはたたれていない状況でした。
そこに、カントというドイツ観念論という潮流を生み出した人物によって、神と哲学が分離されるに至るのです。ここまでが西洋哲学の流れになります。

ギリシャ哲学

そもそも哲学は、紀元前5世紀、アテナイの哲学者ソクラテスから始まったとされます。そこから、ソクラテス、プラトン、アリストテレスの三人がギリシャ哲学の主要人物と言われています。

ここではギリシャ哲学の主要人物である三人に焦点を絞って解説して行きます。
ソクラテス
ソクラテスは、哲学の生みの親と言われる人物です。彼はアテナイの人物です。ではなぜ、ソクラテスが哲学の生みの親と言われるようになったのでしょう。それは、ソクラテス以前は神話のような考え方が中心だったからです。

ソクラテス以前は哲学というよりは神話のような考え方が中心でした。また、彼がいたアテナイでは、ソフィストの弁論術が流行していました。弁論術はあくまで、人を説き伏せる事が目的で真理を追求するようなものではありませんでした。

その中で、ソクラテスは、人間の「正しい在り方」について「対話法」や「無知の知」という考え方を持った人物でした。そして彼の考え方が、これまでの思想のあり方を「哲学」(フィロソフィー)の段階に高めることになりました。
- 神話的な思想や技術としての弁論術が一般的だったギリシャ世界に、「人間の徳」や「正しさ」という哲学的思考を持ち込んだから
ただ、彼はソフィストや政治家等をひたすら対話法を用いて説き伏せ続けていたため、反感を買い死刑になってしまいます。その中で、弟子のプラトンはアテナイの政治に絶望してソクラテスの意志を継ぎ哲学者になる子をを決意したのです。

プラトン
プラトン(Platon 前427~前347)は、アテナイの哲学者です。ソクラテスの弟子でもありました。

当時彼が生きたアテナイの政治は混乱が生まれた時代でした。絶対的な真理など存在しないと民衆を翻弄するソフィスト。そして、戦争。これらの事象によって政治的に混乱が生まれていました。

そこで、プラトンはアテナイの政治に「正しい基準」を設け、平和なアテナイの政治を実現しようとします。そこで生まれたのがイデア論です。イデア(=真実在)とは、現実世界とは「別の世界(イデア界)」にある「究極の理想の存在」のことを指します。
- 現実世界とは「別の世界(イデア界)」にある「究極の理想の存在」のこと
これは、見たり聞いたりすることで感覚で捉えられる個々の事物はすべて仮の姿で、時代を超越した永遠不変の「イデア」が真の実在であると考えたのです。

アリストテレス
アリストテレス(前384年 – 前322年)は、古代ギリシアの哲学者で「万学の祖」です。プラトンの弟子でしたが、彼はマケドニア王国の植民地出身であったこともあり、祖国を持たざる人間でした。

そのため、彼の哲学はプラトンのように「政治的な正しさ」といった思想を持っていませんでした。むしろ一歩引いて物事を捉えようとした点が特徴でした。

その考えが如実に現れているのが四原因説です。。四原因説とは、物事の原因は、質料因・形相因・作用因・目的因の四つから 成り立っているという立場のことです。
- 質料因=材質
- 形相因=形
- 作用因=存在を創り出すもの
- 目的因=存在の目的
現実にあるものに宿る真理を探究するために、あらゆる物事の成り立ちを説明することを目的に生み出されました。まず、「存在しているもの」が何でできているかが「質料因」です。そして、「存在しているもの」自体の本質や構造が「形相因」にあたります。
さらにその事物の運動や変化を引き起こす四原因説は「動力因」(ト・ディア・ティ)です。そして、それが目指しているものが「目的因」(ト・フー・ヘネカ)であると考えました。

中世哲学

中世哲学とは?
中世哲学は、キリスト教の正当性を理論づけ、つまり理性(哲学)と信仰(宗教)の融和を目指している点が大きな特徴です。
- キリスト教は、今からおよそ二千年前に、イエスを創始者とし、ユダヤ教を母胎として発展した宗教です。
トマスは、「哲学は神学の婢(はしため)」と述べています。ここからも分かるように神学が上位に存在し、それを理論づけるサブ的な役割を果たすのが哲学であるという考えが前提となっていました。

これは、いわば信仰(キリスト教)と理性(哲学)をいかに宥和させるかという点が中世哲学の課題でした。
教父哲学
教父哲学は、まだイスラム教などの異教がヨーロッパで幅を利かせていた時代、キリスト教の擁護を目的に、ギリシア哲学を利用してキリスト教思想を説明した点が中世哲学の特徴です。

教父哲学における、教父はキリスト教が広める上で教父(father)と呼ばれる哲学的教養を持ったキリスト者のことです。教父はキリスト教とギリシャ哲学が相反するものではない事を人々に説明することで、キリスト教をヨーロッパに広めました。
- キリスト教とギリシャ哲学の融和を目指しつつキリスト教の普及を行なった教父たちの哲学の潮流
その、教父の中で最大の人物がアウグスティヌス(354年11月13日 – 430年8月28日)です。彼は西ローマ帝国の皇帝で、キリスト教が権威を持つきっかけを作った人物です。

アウグスティヌスは、プラトンのイデア界を神の精神の中に位置付けることでギリシャ哲学とキリスト教の融和を実現しようとした人物でした。

アウグスティヌスは、『告白』『神の国』『三位一体論』などの著作を残しています。彼のキリスト教は正統派の教義として千年近く続くことになります。
スコラ哲学
中世哲学は、アウグスティヌスの教父哲学を基盤に、スコラ学として発展しました。スコラとは学校の意味です。フランク王国のカール大帝が各地にキリスト教の学校を設立して教えを広めたことがら始まります。
- スコラとは学校という意味で、キリスト教を教える学校で広まった哲学の総称
このスコラ哲学の全盛期および完成をしたのが、トマス・アクィナスです。彼は13世紀の哲学者です。イタリアに生まれ、ドミニコ会修道士からパリ大学教授となった人物です。

彼は、アリストテレス哲学をキリスト教信仰に調和させることを目指した人物で、「神の存在証明」を行いました。アリストテレス哲学は、現実の中に真理を見つけ出すことを目指したものです。
トマスの神の存在証明は、簡単にいうと地球や月などの天体が動いているという事実に注目します。そしてこれらには、アリストテレスで言うところの「始動因(動かし始め要因)」が必ず存在するはずで、それが神としか考えられないというものでした。

彼は、アリストテレス哲学を解釈することで、理性と信仰の一致を目指したのです。『神学大全』(1256年)などの著名な著作を残しています。
近世哲学:合理論と経験論

近世哲学の特徴
近世哲学が生まれた時代は、カトリックとプロテスタントの対立から発生した宗教戦争等の影響で、キリスト教の権威が失墜した時代でした。

加えて、16世紀から17世紀にかけて、自然科学の急激な発展が起ります。コペルニクスの地動説やガリレイの物体落下の法則、ニュートンの万有引力の法則があげられます。

そうした中で、聖書などでは神様の存在を信じることができなく成ります。そこで、合理的に神の存在を証明しようとするように成りました。その一つに大陸合理論が挙げられます。対して、イギリス経験論という神の存在自体を徹底した哲学運動も登場し始めたのが近代哲学の特徴です。

- デカルトから始まり、神を前提とした哲学から始まり、経験論という神の存在を否定した哲学が生み出されたのが特徴
大陸合理論
大陸合理論にはデカルト、スピノザ、ライプニッツなどの人物がいます。

彼らは、神が人間に等しく分け与えた理性を使うことで、真理に辿り着くとと考えます。これは、神が照らす光を通して人は、世界を理解できるという神ありきの考えです。

- 神が人間に等しく分け与えた理性を使うことで、真理に辿り着くとと考えている
イギリス経験論
イギリス経験論は、ロック、バークリー、ヒュームなどの人物がいます。経験や感覚、観察、実験に対して絶対的な信頼を置いています。絶対的な心理を見つけ出すことは不可能との立場にあります。

例えば、神様は存在すると思っている国の人がいたとしても、神様という言葉すら知らない別の国の人にとっては知りもしないことです。絶対的真理には辿り着かないという立場に至るのです。

- 神の理性などはなく、人間の認識と経験が全てであるという考え方
近代哲学:ドイツ観念論

時代背景とドイツ観念論
ドイツ観念論が生まれる時代背景には、ドイツの近代化への乗り遅れがありました。イギリスやフランスが産業革命を実現していました。

対して当時のドイツでは封建的な習慣が残り、産業の育成や軍事力の強化がなされていない状況でした。その中で、ドイツでは
その中で、カントの認識論から始まりヘーゲルに至るまでの絶対精神で感性が見られたのがドイツ観念論という潮流です。

カントの認識論を出発点に「自己意識」や「精神」、「自我」などの精神的なものについて理論を展開しているのが特徴です。
- カントの認識論から始まりヘーゲルに至るまでの絶対精神で感性が見られたのがドイツ観念論という潮流
カント
カントは、大陸合理論とイギリス経験論に対してどちらに対しても批判的な立場にあります。これらを統合するような理論を打ち立てたのがカント哲学です。

カントは、合理論に対する批判として、認識の可能性や本質、限界についての考察を欠き、ただ認識能力を信じて知識の無限の妥当性を主張する傾向があり、独断論であるとカントは批判します。
一方、経験論は経験や感覚に主眼を置くため、普遍的な理論の存在に対して否定的でした。そこでカントは、懐疑論と名付けます。これら二つの批判から二つの理論を融合して生み出された理論が以下で解説する『純粋理性批判』です。

彼の『純粋理性批判』がコペルニクス的転回と言われる理由は、これまで「われわれの認識が対象に従う」のではなく、「対象がわれわれの認識に従わなければならない」とする考え方が画期的だったからです

ヘーゲル
ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲル(1770年8月27日 – 1831年11月14日)は、ドイツの哲学者です。

ヘーゲルの『精神現象学』の最も重要なキーワードとして弁証法的統合をあげています。弁証法的統合とは、簡単にいうと対立する物事から新しい見識を見いだす論理のことです。

- 対立する物事から新しい見識を見いだす論理のこと
ヘーゲルは弁証法的統合によって、精神は絶対精神に至ると考えます。
一種共同体的なもの(客観的精神)と個人的なもの(主観的精神)が対立している状況があるとします。これらの相反するものを弁証法的統合をすることで絶対精神に至るのですです。

絶対精神は、存在と認識が一致して、カント流にいうならば物自体の世界に至った状態のことを指します。
- 共同体的なもの(客観的精神)と個人的なもの(主観的精神)が対立している状況から弁証法的統合をすることで至る状態
- 存在と認識が一致している究極の状態
まとめ

いかがでしたでしょうか?西洋哲学の大まかな流れについて理解していただけたでしょうか?主に以下のような流れを辿った西洋哲学でした。
- ギリシャ哲学:哲学の始まり
- 中世哲学:キリスト教と哲学の融和
- 近世哲学:理性優位とキリスト教の影響力の低下
- 近代哲学:神と哲学の分離へ