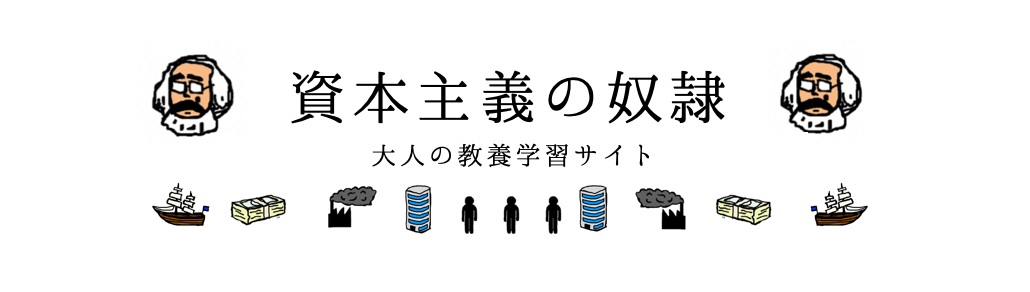デカルトは、「我思う、故に我あり」という言葉で有名な哲学者です。彼の思想は、西洋哲学史の近代化に対して大きな貢献をしました。
そこで、この記事ではデカルトの生涯や思想の概要に触れたのち、デカルトの方法的懐疑、心身二元論という代表的な考え方について解説していきます。
- デカルトの人について知ることができる
- デカルトの代表的な理論である「方法的懐疑」、「心身二元論」について知ることができる
デカルトの生涯

ルネ・デカルト(1596年~1650年)は、近代哲学の祖と言われるフランスの哲学者です。「我思う、故に我あり」という言葉で非常に有名です。
デカルトは1596年に、中部フランスの西側にあるアンドル=エ=ロワール県のラ・エーに生まれました。1606年、デカルト10歳のとき、イエズス会のラ・フレーシュ学院に入学します。学院ではスコラ哲学や、数学、占星術や魔術など秘術の類を学びました。

デカルトは、学院では数学を得意としておりました。その一方で、スコラ哲学や神学に対して懐疑を抱くようになっていました。
こうした背景もあり、1616年、デカルト20歳以降の時に「書物」を捨て「世間という大きな書物」の中に飛び込んでいくようになります。これ以降彼は世界中を遍歴するようになります。
1619年、彼が23歳を迎えた頃に三十年戦争が勃発。デカルトはこれに参加するためオランダを離れドイツへ赴き、バイエルン公マクシミリアン1世の軍に入隊します。そしてその年の10月、彼は哲学することを自身の使命として考え始めます。

そこから、デカルトはいくつかの著作を生み出し「近代哲学の祖」と語り継がれるようになります。
- 『世界論』:地動説を含めた世界観をその誕生から解き明かす
- 『方法序説』:正しい理性を用いて真理を探究する方法、及びその試み。「デカルト座標」の発明。
- 『省察』:『方法序説』をより詳しく専門的にした内容
- 『哲学原理』:デカルト哲学の完成形
デカルトの思想の背景

デカルトは、近代哲学の祖と言われる人物でした。そう言われる所以には、彼が中世のスコラ哲学に対して大きく変更を迫るような理論や著作を生み出したことによります。
では、デカルト以前の哲学はどのありようと、デカルトの思想がどのような変更を迫ったのかを解説していきます。
キリスト教と哲学の結びつき
デカルト以前の哲学は、キリスト教の信仰と哲学の思想がいかに合致しているか(理性と信仰の合致)を説明することを目的としたスコラ哲学が主流を閉めていました。
トマスは、「哲学は神学の婢(はしため)」と述べています。ここからも分かるように神学が上位に存在し、それを理論づけるサブ的な役割を果たすのが哲学であるという考えが前提となっていました。

これは、いわば信仰(キリスト教)と理性(哲学)をいかに宥和させるかという点が中世哲学の課題でした。
- スコラとは学校という意味で、キリスト教を教える学校で広まった哲学の総称。キリスト教と哲学(理性と信仰)の融和を目指した。
キリスト教の凋落と学問の基礎づけの揺ら
デカルトが生きた時代は、カトリックとプロテスタントの対立から発生した宗教戦争等の影響で、キリスト教の権威が失墜した時代でした。

加えて、16世紀から17世紀にかけて、自然科学の急激な発展が起ります。コペルニクスの地動説やガリレイの物体落下の法則、ニュートンの万有引力の法則があげられます。

そうした中で、聖書などでは神様の存在を信じることができなく成ります。そこで、合理的に神の存在を証明しようとするように成りました。その一つに大陸合理論があげられます。
デカルトが学問の基礎づけを試みる
キリスト教の凋落とともに、それをベースとした学問に対する信頼性が失われ始めたのがデカルトが生きた時代でした。そこで、デカルトは学問というものの基礎づけを図るべく思索を続けました。
デカルトは、それまでの「神が真理を照らし出す」(=神を知らない一般人は真理を知ることができない)という考え方の代わりに、「神から与えられた理性」でとことん考えれば誰もが受け入れることのできる地点があるはずだという考え方でした。

イギリス経験論との対立
デカルトは、大陸合理論と呼ばれる哲学の潮流に属しており、神の存在自体を前提としていました。一方で、イギリス経験論と呼ばれる神の存在を否定する潮流が存在しており、批判に耐えるためにデカルトは神の存在証明を行なっております。

- 中世哲学が凋落していく中で生まれた近世哲学の潮流。神が人間に等しく分け与えた理性を使うことで、真理に辿り着くとと考えている
「方法的懐疑」について:コギト・エルゴ・スム

彼は、真理を見つけるためには懐疑的な態度を持つことが重要だと考え、疑うことから始める方法的懐疑を提唱しました。
方法的懐疑とは、すべての知識を疑うことから始め、確実な知識を築いていくための哲学的な手法です。方法的懐疑の基本的な考え方は以下のような流れで行われます。
感覚や経験への懐疑
デカルトは、日常の経験や感覚が時に誤解を生み出すことに気づきました。
例えば、夢の中で現実の出来事を経験しているように感じることがありますが、それは実際には現実ではないことが分かります。このような例から、私たちの感覚や経験には誤りが含まれている可能性があることに気づきます。
ここから、感覚や経験には共通了解が存在しないことがわかります。
伝統的な知識への懐疑
次に、デカルトは伝統的に受け入れられてきた知識にも疑問を投げかけました。例えば、先人の哲学者たちが示してきた考え方や科学的な理論にも、誤りがある可能性を考慮しました。
彼は、根本的な疑問を抱くことで確実な真理を見つけることができると信じました。
神の存在の否定
デカルトは神や超自然的な存在についても疑いを持ちました。彼は、「全能なる神が私を欺くことはないだろう」という信念に基づき、神が私たちを騙すことはないと考えました。
したがって、神があるという前提を捨てて、完全に独立した自己の存在を前提にしたのです。最終的に、デカルトは「我思う、故に我あり(Cogito, ergo sum)」という有名な言葉で示される自己存在の確立に至ります。
彼は、疑うことができるということは、少なくとも思考する自己が存在するということを意味すると結論づけました。思考する自己が確立されることで、少なくとも一つの確実な真理を見つけたということになります。
「心身二元論」について

一元的物質論への批判
デカルトの心身二元論は、当時主流であった一元的物質論(物質のみが存在し、心や意識は物質の副産物として説明される)と対立しています。
彼は、心的な経験や意識を物質的な説明だけでは十分に説明できないと主張し、心と身体を別々の領域として捉えました。
心身二元論とは
デカルトは、心(精神)と身体(物体)は本質的に異なる存在であると考えました。心は思考、感情、意識などの心的な性質を持ち、身体は物理的な性質を持つものと見なされます。
デカルトは、心と身体が別々の実体であるとしても、相互作用があると考えました。つまり、心が身体に影響を与えることも、逆に身体が心に影響を与えることも可能であると考えたのです。
神による結合
デカルトは心身の結合を説明する際に、神による介入が必要だと考えました。つまり、神が心と身体を結びつけて相互作用が可能にしているという信念に基づいていました。
しかし、具体的にどのようにして心と身体が結びつくかについて松果体を通しているという、現在ではあまり説得力のないものになっています。ただ、心身二元論はこれまでの、物質一元論に変更を迫るインパクトを与えました。
まとめ