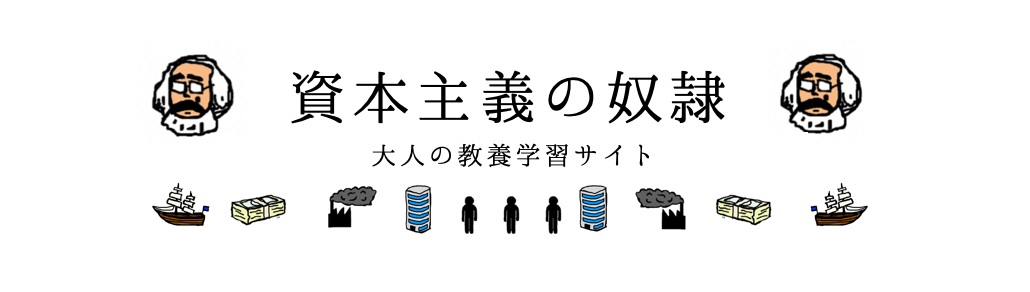アリストテレス、ヘーゲル、カントが積み上げてきた西洋哲学。マルティン・ハイデガーは、過去の西洋哲学の根本的な問いが「存在とは何か?」であったと主張します。
我々の日常生活を徹底的なまでに抽象化し「存在」という概念のを深く分析しました。これまでの西洋哲学に激震を走らせたのがハイデガーです。特に、その激震を走らせたのが未完の著作『存在と時間』(1927年)でした。
そこで、この記事ではハイデガーその人と、彼の思想が凝縮された『存在と時間』についてわかりやすく解説していきます。最後までお付き合いいただければと思います。
- マルティン・ハイデガーその人について知ることができる
- ハイデガーの主著である『存在と時間』について知ることができる
ハイデガーの生涯

マルティン・ハイデッガー(Martin Heidegger, 1889年9月26日 – 1976年5月26日)は、ドイツの哲学者です。

ハイデッガーは、1889年に帝政ドイツ南西部のバーデン大公国ウュルテンベルク州の小村で生まれました。彼は、1909年にカトリック系のフライブルク大学神学部に入学しますが、途中で哲学部に転部します。指導教官は当初シュナイダーと言う人物でしたが、途中から現象学を打ち立てたフッサールに支えるようになります。
その後、1919年にフッサールの助手をしながらカトリック系のフライブルク大学の教壇に立つようになります。1922年には『ナルトプ報告』と呼ばれる『存在と時間』の元になる論文も執筆しています。
しかし、フライブルク大学でのポストに恵まれず、『ナルトプ報告』を高く評価したプロテスタント系のマーブルク大学の助教授に1923年に就任します。ただ、次第にプロテスタント系の人たちと距離を置くようになり、形而上学への傾倒を深めていきます。

そうした中で執筆されたのが『存在と時間』(1927年)でした。これによりハイデガーは大きな名声を手に入れることになります。そして1928年には、師匠であるフッサールの退任をきっかけにフライブルク大学の正教授のポストを手にいれることになるのです。

1929年の世界金融恐慌によって失業率が急増し、国民社会主義ドイツ労働者党(ナチス)がドイツ国内で勢力を伸ばし始めます。そうした中で、ハイデガーはナチス党へと加担する動きを見せ始め、戦後大きな論争を巻き起こしました。
ハイデガーの思想

『ナトルプ報告』による既存の存在論への批判
『ナトルプ報告』を通して、アリストテレスなどのギリシャ哲学における存在論への批判が行われ、ハイデガー独自の存在論を展開されました。
アリストテレスから始まりカントに至るまで、「存在は制作されたもの」と言う認識があるとハイデガーは指摘します。

逆にアリストテレス・プラトンのギリシャ哲学以前までは、存在は制作されたものではなく、存在は生成(生まれ出てくる)すると言う考えでした。これを「存在の忘却」とハイデガーは表現しています、。
『ナトルプ報告』を通して、ハイデガーは「存在は制作された」とい西洋哲学の思想を批判し乗り越えようとしたのです。
ハイデガーの研究手法:現象学
まず、ハイデガーは現象学の祖であるフッサールの影響を多分に受けた人物でした。そのため、ベースには現象学があり、ハイデガーはそれを批判する形で理論を展開しました。

ハイデガーの現象学とフッサールの現象学は、そもそも目的が違います。フッサールは学問を基礎づけるための方法として現象学を考えていました。一方の、ハイデガーは人間の在り方を探究するための方法として現象学を考えていた点が異なります。
まずフッサールは近代哲学側に与しています。そのため、意識や自我を中心とした現象学の位置付けでした。しかし、ハイデガーはのちにも述べるようにギリシャ哲学〜近代哲学の批判を目的に現象学を研究手法として取り入れる点が違います。
 |  | |
|---|---|---|
| 方法論 | フッサールの現象学 | ハイデガーの現象学 |
| 目的 | 学問の基礎づけ | 人間の在り方の探求 |
| スタンス | 近代哲学側から 意識や自我を中心に分析 | ギリシャ〜近代哲学 を批判 |
『存在と時間』の構成

『ナトルプ報告』でのギリシャ哲学以降の西洋哲学の存在論への批判をさらに広げる形で展開されたのが『存在と時間』です。『存在と時間』では純粋に「存在とは何か?」という点に関して淡々と述べられます。
当初、『存在と時間』は、以下のような構成で執筆が進む予定でした。
- 第1部 現存在の解釈と時間の解明
- 第1編 現存在の基礎分析
- 第2編 現存在と時間性
- 第3編 時間と存在
- 第2部 存在論の歴史の現象学的解体
- 第1編 カントの時間論について
- 第2編 デカルトの「我あり」と「思う」について
- 第3編 アリストテレスの時間論について
結局、書かれたのは第1部の第2編現存在と時間性まででした。しかし、「存在一般の意味」を解き明かすには至りませんでした。とはいえ、現存在というものに対する緻密な分析は、哲学界に大きな衝撃を与え、のちの哲学の潮流を大きく変えることになります。
『存在と時間』①:存在とは何か?

『存在と時間』は以下のプラトンの『ソフィステス』の引用から始まります
「『ある』という言葉でもってわれわれが一体なにを思い描いているのか、という問いの答えを、今日われわれは持っているだろうか? われわれはいままでその答えを持っていると思い込んでいたのに、いまではまったく心もとなくなっている。」
『存在と時間』は、「ある(Sein)」ということはどうゆうことなのか、という点を明らかにする事を目的とした著作です。また、本作でハイデガーは「存在者」と「存在」の違いを明確にしています。
例えば、コップは存在者です。その他に生物、家具等も存在者になります。しかし、これらが「ある」という点は存在者とは異なるものです。ハイデガーが探求の対象としたのはこの「ある=存在」を対象としました。

そして、この「ある=存在」を内省的に意識することができるが人間であり、ハイデガーはそれを「現存在(dasein)」と名付け分析対象としました。
- 『存在と時間』では、「存在」を研究対象としている
『存在と時間』②:現存在(=人間)の分析

「ある=存在」について、人間が唯一、「自分がどんな存在か」を考えることができます。こうした、人間のような内省的な意識を持つものを「現存在(dasein)」といいます。

その上で、ハイデガーは『存在と時間』で「現存在」というものがどうゆうものかを徹底的に分析しました。『存在と時間』における現存在の分析では、「われわれは世界の中にいる」という私たちが感じる現象自体から現存在の分析が始まります。
- 人間のような内省的な意識を持つもの
まず、現存在には世界=内=存在という構造が前提としてあるとします。簡単にいうと、世界の中で常に特定の状況や背景、他の存在者との関係性の中で存在しているといったことです。世界=内=存在には、以下のような三つの特徴があります。
- 道具-配慮
- 共同存在-顧慮
- 内存在
これらの三つによって世界内存在=「我々は世界の中にいる」というものが成立します。

道具-配慮
世界内存在における「世界」は現存在にとってどのように現れてくるかという点を、ハイデガーは「道具」を介して現れてくると指摘します。

現存在が何かをしようと目的を持っていた場合、「身の回り(環境世界)」にある道具が必要になります。例えば、ハンマーは物を砕くためにあります。これは、現存在が物を砕くという目的に適った物だから道具として使われるのです。

そこで、目的に即して有意義であると捉えることを配慮と言います。現存在は「配慮」を通して道具と出会い、それを繰り返す中で世界性一般の理念に到達するとハイデガーは考えたのです。
- 現存在の意図する目的にかなうモノ
- 世界が現れてくる契機となる
共同現存在-顧慮
続いて、世界=内=存在における共同現存在という構造についてもハイデガーは言及しています。共同存在は、「『われわれ』は世界の中に『いる』」という「現象」に関わることです。
ハイデガーは、他人のことを共同現存在と言います。世界内存在にとっての世界とは、そもそも他人を含んだものです。

そうしたときに、現存在は、道具的存在者に対しては配慮を通して関わりますが、共同現存在に対しては別のやり方で関わります。それが「顧慮」です。
例えば、農夫が畑を耕すのは土地が道具的存在である配慮からくる行為です。同時に、農夫が他の畑を踏まないように歩くのは共同現存在である他人を意識して歩きます。こうした現存在が共同現存在に気を配るような行為を顧慮と言います。

- 「『われわれ』は世界の中に『いる』」という「現象」に関わること
- 共同存在に対して現存在は常に「顧慮」して入りう
内存在
このように、「道具」や「共同現存在」といわれる他者とその関係性の中で、現存在は「なじんで」います。なじんでいるとはどういう事なのか。
内存在は、「了解-語り-情状性」といったあり方をしており、例えば「語り」であれば共同現存在とのうわさ話やおしゃべり等のかかわりの中で日常を過ごしています。それは道具への配慮であったり、共同現存在への顧慮などがあるでしょう。
現存在が「なじんでいる」平均的な日常において、世人(パンピー位な意味でいいです)に「頽落(たいらく)」しています。主人公である現存在がモブキャラになってるくらいの意味です。

そして、配慮的に気遣われた「世界」のもとに没入しているのです。この状態は必ずも良い状況ではなく、「本来的な自己」から逃げるように、「世人」という在り方に頽落している状況と言えます。
関心(気遣い)
ハイデガーは、世界=内=存在の各構造全体を統一するものが「関心(気遣い)」としています。これは、何となく「興味をもつこと」的なニュアンスのあるものです。
現存在とは、「開示態」というあり方をしています。これは、今の自分より先にある可能性を掴みとろうとするありようの事を指します。このような現在の自分に先立つもののことを「関心」と名付けました。

現存在は平均的日常において世人に頽落していますが、現存在には本来的に関心(気遣い)という構造があり、あらゆる可能性に向かって自由に行動(投企)していくのです。これによって本来的な自己を取り戻していくのです。
- 世界=内=存在の各構造全体を統一するもの
- 現存在には本来的に関心(気遣い)という構造があり、あらゆる可能性に向かって投企する
『存在と時間』③:現存在と時間の関係性

ハイデガーは、現存在の分析の結果、関心(気遣い)という構造がある事を明らかにしました。ただ、これは平均的な日常における現存在の在り方を示したにすぎません。
ハイデガーはここから進んでより「根源的」な現存在の在り方を提示しようとしました。
それが、時間と現存在の関係性です。現存在は、生まれて死ぬことで存在は失われます。つまり、時間は有限です。しかし、平均的な日常で人々は時間は無限にあるように考えられます。その中で、時間は過去・現在・未来というように観念されます。
しかし、時間が有限であると考えれば有意義に生きようとするものです。有意義に生きようとすることで、将来の可能性に向かって行動(投企)しようとするのです。そうすることで、現存在が本来的な自己を全うすることができるとハイデガーは考えたのです。
さいごに

我々の日常生活を徹底的なまでに抽象化し「存在」という概念のを深く分析しました。これまでの西洋哲学に激震を走らせたのがハイデガーです。特に、その激震を走らせたのが未完の著作『存在と時間』(1927年)でした。
そこで、この記事ではハイデガーその人と、彼の思想が凝縮された『存在と時間』についてわかりやすく解説していきました。
実際に、『存在と時間』を読むと難解な言い回しに困惑するかもしれません。その時はこの記事に戻っていただけると理解が深まると思います。