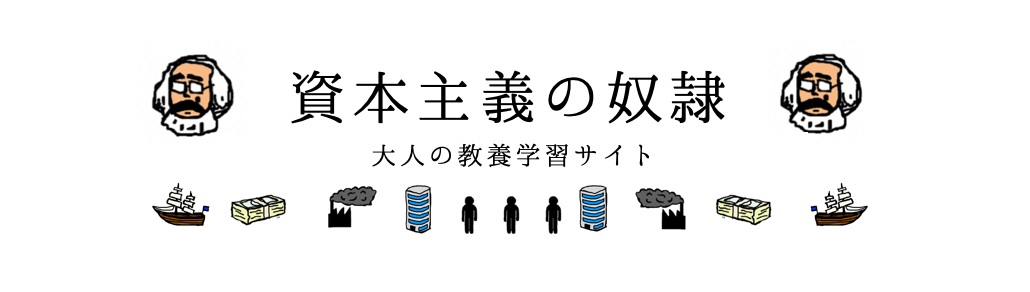この記事では、近年話題のDeFi(分散型金融)についてわかりやすく解説していきます。
この記事を読む時に最低限知って欲しいこととして、DeFiとは
既存の金融仲介業の存在を無効化するアプリケーション、もしくは金融サービスのことを指し示します。
であるということです。さらに詳細については以下で解説します。よろしければ最後までお付き合いください。

この記事は、経済オタクで仮想通貨にハマっている資本主義の奴隷編集部が解説しています。
- 仮想通貨初心者が中級者にアップする上で重要な情報を知ることができる
- DeFi(分散型金融)の具体的な事例を知ることができる
DeFi(分散型金融)とは何か?

DeFi(分散型金融)とは
DeFiとは、Decentralized Financeの略で、和訳すると分散型金融になります。
分散型金融とは、簡単にいうと、既存の金融仲介業の存在を無効化するアプリケーション、もしくは金融サービスのことを指し示します。これらをCeFi(Centralize Finance)とも呼称されます。
DeFiとは、金融機関のように中央の管理者を必要とせず自律的に運営され、パブリック型ブロックチェーン上でスマートコントラクト(あらかじめ決められた条件を満たした場合にのみ契約を自動的に執行する仕組み)を活用して構築・運用される分散型の金融サービスのことです。
出典:NTT DATA「DeFi(分散型金融)とともに描く新しい金融サービス」

既存の金融(CeFi)との違い
既存の金融機関(銀行、生命保険会社、証券会社)などは、取引の仲介をして手数料をユーザーから取ることで売上を上げてきました。これらをCeFi(Centralize Finance)とも言います。
DeFi(分散型金融)は、仲介業者としての機能を果たすCeFi(中央集権型金融)をスマートコントラクト機能で不要にし、ユーザー同士での取引を可能にするのです。

DeFi(分散型金融の仕組み)

ブロックチェーン上で展開されている
世界にはさまざまなブロックチェーンが開発されています。DeFi(分散型金融)は、これらのブロックチェーン上に展開されています。そして年々その数は増え続けています。
そもそもブロックチェーン上では、dAppcs(分散型アプリケーション)が展開可能です。そのうちの一つとしてDeFi(分散型金融)系のアプリケーションが展開されています。

また、DeFi(分散型金融)は一つのブロックチェーンだけでなく、複数のブロックチェーン上で展開される事例もあります。

スマートコントラクトによって実現
DeFi(分散型金融)が実現するためには、スマートコントラクトというプログラムが必須でした。ブロックチェーンはただのデータベースです。スマートコントラクがあるからこそデータベース上でサービスが展開できます。
スマートコントラクトは、ブロックチェーン上にプログラムを書き込むことで、設定した条件を自動的に実行します。これにより取引(トランザクション)を自動化することができます。
事前に取引内容を決め自動的に取引が実行されることで取引効率が高めることができます。

これにより、先に説明したブロックチェーン上で展開することができるようになったのです。
DeFi(分散型金融)はスマートコントラクトによる取引の自動化によって実現可能に
DeFi(分散型金融)の事例

DeFi(分散型金融)において
- DEX(分散型取引所)
- ICO(新規通貨公開)
- レンディングプロトコル
- ステーブルコイン
分散型取引所(DEX)
DEX(Decentralized Exchange:分散型取引所)とは、中央管理者が存在しない仮想通貨取引所です。
従来の取引所はDEXに対してCEX(Centralized Exchange)と呼ばれています。CEXは、特定の企業によって取引所が中央管理者によって管理されています。
中央管理者が存在しない無人の仮想通貨取引所です。仲介者を挟まず、ユーザー同士での取引が可能。

一方で、DEXでは企業などの中央管理者を介することなくユーザー同士での取引が実現されます。
ICO(新規通貨公開)
ICOとは、イニシャル・コイン・オファリング(Initial Coin Offering)の略称になります。和訳すと新規通貨公開です。クラウドセール、トークンセールとも言われます。
簡単にいうと、企業(もしくは個人)が独自の新しい仮想通貨を発行し、販売することで、資金を調達する仕組みのことです。
企業(もしくは個人)が独自の新しい仮想通貨を発行し、販売することで、資金を調達する仕組みのことです。
既存のやり方ですと、企業はさまざまな方法で資金調達をします。一般的な方法は、銀行から借り入れるか、株式を公開して資金調達を行う方法がありました。

これを仮想通貨で実現したのがICOです。企業や個人であろうと誰でも、独自のコインを発行して、それによる資金調達が可能になったのです。
レンディング(貸仮想通貨)
レンディング(貸仮想通貨)は、暗号資産の貸し手と借り手をつなぐDeFiサービスです。
簡単にいうと、仮想通貨版の銀行みたいなものです。貸し手レンディングの取引所の口座にイーサを預け、取引所はイーサを借りたい人に貸すという仕組みです。
貸し手レンディングの取引所の口座にイーサを預け、取引所はイーサを借りたい人に貸すという仕組みです。

ステーブルコイン
ステーブルコインは、仮想通貨の価格の不安定性を解決するために生まれた仮想通貨です。ステーブルは安定、コインは仮想通貨で、ステーブルコインです。De
ステーブルコインは、仮想通貨の価格の不安定性を解決するために生まれた仮想通貨
ステーブルコインが安定する理由には、既存の法定通貨やその他の仮想通貨などと価値が連動しているからです。この価格の安定性において

DeFi(分散型金融)のこれまで

DeFiはこれまでどのような道を歩んできたのでしょうか?ここではDeFiの歴史を振り返っていきます。
また、DeFiのこれまでの流れをまとめた図を参考に読み進めてみてください。

DeFiの始まりはICOとDEX:2016〜2018年
DeFiが利用された事例としてICOとDEXが挙げられます。
ICOの始まり
DeFiの始まりとして、2016年から2018年始め頃まで、イーサリアムを利用するアプリケーション開発チームが資金調達のためにICOを行ったことが挙げられます。

その結果、ICOにより誕生した数多のトークンへの需要が生み出されます。
トークン需要の高まりの中で生まれたDEX
ICOによる資金需要が生まれた中で、Binanceや国内ではCoinCheckなどの取引所の仲介を必要とせず、スマートコントラクト機能により取引ができるアプリケーションも生まれました。それが、DEX(分散型取引所)です。
2017年には EtherDelta(イーサデルタ)、Bancor(バンコール)、2018年には Kyber Network、0x projectのようなDEXが現在は稼働しています。

このICOやDEXの登場によって、DeFiの基盤は一通り揃いました。
DeFiの拡大:2018年〜
その後、2018年頃からは、DEXだけでなく、より複雑な金融機能を有したプロダクト開発が進展しました。
Telegramというチャットアプリでの議論や情報交換から始まりました。
次第にハッカソン等のイベントを通じて、DeFiの開発コミュニティーが資金や開発においてお互いに助け合うというのが通例になっています。

この頃からDeFiという名前が使用されるようになったのもこの時期のことです。
DeFiの欠陥の露呈:2020年〜
2020年に入ると、DeFiエコシステムが大きく展開していきました。種類も豊富で資金が集まりました。
ですが、それによりDeFiに集まった資金をハッキングしようとする動きも出てきます。それが、以下の二つです。
- bZxのFulcrumのフラッシュローンハック
- MakerDAOのブラックスワン事件債務超過
bZxのプラットフォームFulcrumはフラッシュローンはっくという手法でハッカーが2020年に攻撃され被害総額は100万ドルにも及んだそうです。また、MakerDAOは債務超過に陥ったこともありました。

これらの事件は、いまだにDeFiには課題があることを教えてくれる事件でしたあ。
DAOとガバナンストークンの隆盛:現在
2020年の中頃からCompoundが利用者に対してガバナンストークンCOMPの配布を始めます。
ガバナンストークンとは、DAO(自律的分散型組織)においてサービスの運用や開発についての方針を投票で決定するためのトークンです。

これにより、COMPに大きく資金が移動しました。その後、Uniswap(UNI)をはじめとするDEXもトークンを発行し始めました。
COMPは、当初は約11億円ドルほどの運用総額でしたが、4ヶ月ほどで10倍にも膨れ上がりました。
現在では、プロトコルの方向性を決定し、場合によっては収益配分が見込めるガバナンストークンがDeFiにおける重要な存在を担っています。
DeFi(分散型金融)で有名なプロジェクトの事例

Uniswap
Uniswap(UNI:ユニスワップ)とは、2018年11月にローンチDEX(分散型取引所)であり、DeFiアプリケーションです。
また、Uniswapはイーサリアム上のブロックチェーン上に展開されたDEXです。
- Uniswapはイーサリアム上のブロックチェーン上に展開された、管理者のいない分散型取引所(DEX)
- ガバナンストークンUNIを持つことでユーザー自身が、Uniswapの運営に携われる
DEXであるが故に、管理者が存在せずユーザーたちによる運営が実現しています。ガバナンストークンUNIを持つことでユーザー自身が、Uniswapの運営に携わることができます。

また、Uniswapと似たような分散型取引所にはSuhiSwapとかPancake Swap、Balancerなどがあります。ただ、Uniswapはその中でも群を抜いて人気のあるDEXと言って良いでしょう。
Pancakeswap
PancakeSwap(パンケーキスワップ)は、2020年にローンチされたDEX(分散型取引所)です。
また、Pancake swapに対して流動性を提供すると獲得できるのが、CAKEというトークンです。

DEX(Decentralized Exchange:分散型取引所)とは、P2Pネットワークを導入した分散型の仮想通貨取引所です。仲介を挟まずユーザー同士での取引が可能になります。
SushiSwap
SushiSwap(SHUSHI)は、匿名の開発者Chef Nomi氏によって2020年8月にローンチされたDeFiプロジェクトです。
SushiSwapは、中央の管理者がおらず、ユーザー同士での取引が可能なDEX(分散型取引所)になっています。

また、SushiSwapを中心に以下のようなプラットフォームを提供しています※のちの解説。
- Kashi(貸し):レンディン
- Onsen(温泉):流動性マイニング
- SushiBar:ステーキング
- MISO(味噌):IDO:Initial DEX Offering)
- SHOWYOU(醤油):NFTプラットフォーム
ヴァンパイヤ攻撃とは、オープンソースコードをコピーして機能を丸パクリし、その代わりユーザーに何かしらのインセンティブをつけ差別化を図ることで、コピー元のユーザーや流動性を奪い取る攻撃のことです。

ヴァンパイヤ攻撃は成功し、SushiSwapは多くのユーザーと流動性を獲得することに成功しました。
DeFi(分散型金融)のリスクやデメリット

法整備が進んでいないので自己責任
DeFiでは、先にも解説したようにハッキングや債務超過など多くのリスクを抱えています。DeFiはまだ法整備が進んでいないこともあり、サービスの利用中に起こったトラブルは、全てユーザーの自己責任となってしまいます。
既存の金融機関では、いざという時にも保証制度などが整っていますが、仮想通貨関連の法整備は進んでいないのが現状です。この点を考慮した上で、DeFiでの資産運用をする必要があります。
バブル崩壊のリスク
DeFiの現状の値上がりは、バブルである可能性があります。バブルであることは、バブルになってからでないと分かりません。
現在過剰に注目を浴びている可能性も高いので、その点は考慮する必要があります。
- トラブルは全て自己責任
- バブルである可能性も存在する
さいごに

この記事では、近年話題のDeFi(分散型金融)についてわかりやすく解説していきました。
まとめると、DeFIとは以下のような意味になります。
既存の金融仲介業の存在を無効化するアプリケーション、もしくは金融サービスのことを指し示します。
DeFiは現在ではもはや当たり前の存在になりつつあります。ただこれからもWeb3.0の世界を支えてくれる存在になるでしょう。