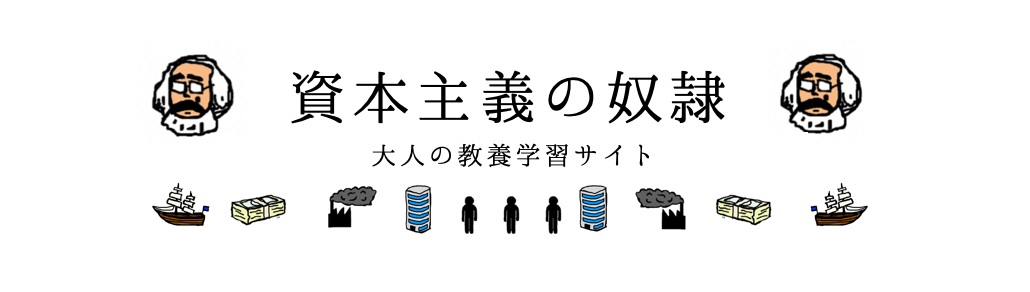この記事では、20世紀はじめの第一次世界大戦、世界大不況、第二次世界大戦におけるヨーロッパの経済を取り扱います。
特に、20世紀はじめはヨーロッパの没落と言われるように、経済の中心がアメリカ合衆国へと移っていた時代でもあります。
また、この記事は以下の書籍を参考に作成しています。西洋経済史をわかりやすくまとめた教科書的な書籍です。よかったら併せて読んでみてください。
自由主義から国家による経済の介入へ

まずは、ここでは20世紀のヨーロッパ経済の全体的な特徴を解説します。
20世紀、第一次世界大戦により、経済や政治の秩序は大きく揺らぐようになります。第一次世界大戦を通して、自国に被害を被ったヨーロッパは経済的な地位が落ち込むようになります。
結果として、大戦で大きな被害を受けなかったアメリカ合衆国やソビエト連邦が世界の中心をになっていくようになります。
経済観の転換
こうした中で、20世紀のヨーロッパにおける経済観は大きく転換するようになります。それは、自由主義的な経済観から、国家介入型の経済観への転換です。
19世紀までは、イギリスを中心として自由貿易主義と、市場介入を控えて安全保障や警察機能に抑えた夜警国家が理想とされました。つまり、アダムスミスの市場放任主義を軸とする考えです。

20世紀になると、国家による経済への介入をよしとする経済観が出てくるようになります。

こうした経済観を主張する人物としてジョンメイナードケインズがいました。ケインズに関しては以下の記事で細かく解説しています。
国家の経済への積極介入には、2つの要素を挙げることができます。それが
- 福祉国家化
- 管理経済体制
です。それぞれ解説していきます。
20世紀になると、国家による経済への介入をよしとする経済観が出てくる。
福祉国家化
1つが、福祉国家化です。労働運動や社会主義運動の中で社会保障の充実が求められるようになります。
この流れに国家は対応する形で、これまで保護の対象外となっていた民衆(労働者)への保護と関与が始まりました。
また、20世紀は大衆社会が始まった時代でもあり、失業率が非常に高い時代でした。こうした時代の要請から、国家は福祉国家という形で経済への介入を深めていったのです。

管理経済体制
2つ目が管理経済体制への移行です。19世紀までは金本位制でした。金本位制とは、金を基準に貨幣の価値を定める体制のことです。貨幣は中央銀行に持って行けば金と交換できたのです。
しかし、世界大恐慌の中で、政府が自由に貨幣を発行できる体制、つまり管理通過体制へと突入します。19世紀までは、金を基準に貨幣の価値を定めることができましたが、20世紀以降は政府が貨幣の価値をコントロールできるようになったのです。

- 福祉国家化:労働運動や社会主義運動の中で社会保障の充実が求められるように
- 世界大恐慌の中で、政府が自由に貨幣を発行できる体制、つまり管理通過体制へと突入
第一次世界大戦とヨーロッパ経済

20世紀はじめは
- 第一次世界大戦による総力戦体制
- ソビエトの発足
が特徴として挙げられます。また、第一次世界大戦の終結によってドイツの賠償問題が次の大戦のきっかけにもなりました。
第一次世界大戦
1914年7月28日、セルビアに対するオーストリアの宣戦布告によって第一次世界大戦が始まりました。大戦の引き金を引いたのはオーストリア皇太子暗殺事件(サラエボ事件)で、多様な民族で構成されるバルカン半島で発生しました

この戦争はヨーロッパ全体を巻き込む戦争に発展します。この戦争は同盟国陣営と連合国陣営の対立という構図へと変わっていきます。
同盟国陣営は、ドイツやオスマン帝国、オーストリアでした。一方で、連合国陣営には、イギリスとフランス、イタリア、ロシアで構成されていました。

大戦は当初、数ヶ月で終結するものと思われていました。しかし、これまでにはなかった、戦車や航空機、毒ガス兵器といった大量破壊力を持った近代兵器の登場によって戦線は硬直し長期化をしました。

- 1914年7月28日、セルビアに対するオーストリアの宣戦布告によって第一次世界大戦が始まる
- 大量破壊力を持った近代兵器の登場によって戦線は硬直し長期化
戦時計画経済と総力戦
交戦各国は、この長期化した戦争を総力戦で切り抜ける必要性が出てきました。なぜなら、戦争の長期化と近代兵器のコストの高まりがあったからです。
そこで、諸国は国民経済を統制・組織化するようになります。軍需物資の生産や兵員輸送の効率化を目的に戦時統制や戦時計画経済が採用されることになりました。
19世紀までの自由主義的な思想は影を潜め、自由放任主義経済から計画経済への移行が、第一次世界大戦によって引き起こされたのです。以下では、各国の様相について見てみましょう。
- 戦争の長期化に伴い、国家は、国民経済を統制・組織化するように。
- 軍需物資の生産や兵員輸送を目的に戦時統制や戦時計画経済が採用される
大戦の終結とドイツ賠償問題
戦局の帰趨は、結局国による補給能力によって決まることになり、先に補給が尽きようとしていた同盟国側が自壊していくことになりました。
1919年のパリ講和会議で締結された、ベルサイユ講和条約によって第一次世界大戦は終結に向かいました。主役は合衆国のウィルソン大統領を中心に開催されました。

ドイツは自国領土の割譲、海外領土、経済権益の没収をされました。しかし、それにとどまらず賠償金義務を貸され、その金額は1320億金マルク(330億ドル)に登りました。
相当な金額であったため、ドイツは戦後支払いが滞ることがありました。それに対して、1923年にはフランスはルールを占領し、軍事的緊張が高まりました。
そこで、アメリカはドーズ賠償案を提示し、アメリカ資本のドイツへの貸付とドイツによる賠償金支払い、連合国による退位米債務支払いとを連結させる仕組みを作り、一時的に軍事的緊張は解かれました。

しかし、この事態は一時的な応急処置でしかなく、のちに世界恐慌の中で瓦解することになりました。
とはいえ、この多額の賠償によってドイツはハイパーインフレに悩まされることになります。これがのちのナチスドイツを生み出す要因になったと言われています。
- ドイツの賠償金がのちのヒトラーの登場を促すことに
- ドーズ賠償案も一時的な応急処置に過ぎなかった
2つの大戦のはざま

第一次世界大戦と第二次世界大戦の間は、戦争のない平和な時期が続きました。この時期、ヨーロッパは復興を遂げ、アメリカは繁栄を謳歌することになりました。
この中で
- 西洋の没落
- 大衆社会の登場
- 企業の性質の変化
が起こりました。それぞれ見ていきましょう。
大戦後の「西洋の没落」
大戦を通して、ヨーロッパ諸国はアメリカに多くの借金を負うことになりました。結果、ヨーロッパは債権国から債務国へと転落します。一方で、アメリカは債権国として大きく成長を遂げます。
第一次世界大戦前は世界貿易の中心はヨーロッパでした。また、国際投資も戦前は9割以上がヨーロッパからのものでした。しかし、大戦によって、国際経済秩序は解体され、ヨーロッパは凋落していくのです。
大衆社会の登場と社会運動の高まり
ヨーロッパの経済的地位が低下するのと並んで、大戦前の経済的富裕層の没落が進みました。イギリスでは大規模地主の没落、ドイツでもユンカーの没落が始まりました。
さらに、大戦後の累進課税方式の所得税や相続税が急富裕層の解体に拍車をかけました。その中で、大戦前に残っていた身分制の残滓は消滅しました。結果、富の平準化が進み大衆社会が到来したのです。

とはいえ、この時期の大衆の経済的状況は恵まれたものではありませんでした。特に1920年代から失業が社会問題となっていました。ドイツでは、1926年に失業率が16%を記録していたのです。その他諸国でも10%を超えている国もありました。
また、この中で、1920年代には労働運動が高まり、各国はこれに呼応して社会政策の拡充を進めました。先に述べた福祉国家化です。
フランスでは、8時間労働日と団体協約制度が法制化されました。イギリスでも義務教育の延長や、保険証の設置がなされました、さらに8時間労働と賃金引き上げに加え、失業保険制度が大幅に改善されたのです。
しかし、この大衆化の流れの中でファシズムが台頭し、ムッソリーニやナチス党のヒトラーが民衆の心を捉えていくようになります。この大衆社会とファシズムは実は非常に相性がよかったのです。

- ヨーロッパの経済的地位が低下するのと並んで、大戦前の経済的富裕層の没落が進みました。
- 富の平準化が進み大衆社会が登場。しかし失業率は依然として高い
アメリカの繁栄:狂騒の20年代
ヨーロッパの復興が始まった1920年代、アメリカは好況に沸いていました。住宅建設と耐久消費財(冷蔵庫とかラジオとか)の需要を基礎にアメリカは堅調に経済発展を遂げます。この時代のアメリカを狂騒の20年代と表現することもあります。
第二次産業革命で生まれた、自動車や化学繊維、電機などの新産業も脚光を浴びるようになります。
特にこの時代のアメリカの繁栄を特徴づけるのが、自動車産業です。ヘンリーフォードは1908年に実用的なT型自動車の販売を始めました。

さらに、ベルトコンベアによる大量生産体制を始めました。これにより製品低価格と高賃金の両方を可能にしたのです。1930年代の登録自動車台数は2600万台にのぼったと言われています。

住宅建設と耐久消費財(冷蔵庫とかラジオとか)の需要を基礎にアメリカは堅調に経済発展を遂げます。この時代のアメリカを狂騒の20年代と表現することもあります。
大企業体制と経営管理
この時期、企業も大規模化が進展しました。チャンドラーは、
企業管理組織は職能未分化の単一事業組織→集権的職能部門制→分権的事業部制
という発達プロセスを遂げると指摘しています。
単一事業組織とは産業革命当時の企業が該当します。この頃は、まだ小規模で経営職能の専門化をする必要性がありませんでした。しかし、19世紀に、鉄道会社では集権的職能部門制という階層管理組織が生まれました。

1920年代には、企業は事業の多角化をはじめ、集権的職能部門制でも問題が出るようになります。ゼネラル・モーター(GM)やゼネラル・エレクトリック(GE)は複数の製品を取り扱うため、多角化を進めました。
そこで、必要となったのが複数の職能を包摂した事業部を本社がさらに統括し、事業部の自立性を認める分権的事業部制が形成されるようになったのです。

GEでは高級乗用車や大衆むけ乗用車、トラックなどの商用車を販売していました。デュポン社では、ダイナマイトや、塗料や接着テープなどの民需品の販売を行なっていました。このような多様な製品を集権的に管理することは不可能になっていたのです。
20年代、事業の拡大により分権的事業部制が採用されるようになる。
所有と経営の分離
経営の大規模化は所有と経営の分離を促進しました。
企業組織が大規模化すると、それだけ巨額資金が必要になります。そこで、不特定多数の個人投資家が少額の株式を所有するようになります。そうなると、自社株の大半を所有した経営者の地位は低下することになります。

結果として、株式をそこまで持っていない専門的経営者による経営支配が強まっていったのです。
事業の拡大は所有と経営の分離を招いた
世界大恐慌

戦間期と言われる時代、1920年代まではアメリカの繁栄など好況を呈していました。しかし、1930年だいに世界大恐慌が起こります。これにより、国家による経済への介入が強まっていくことになります。
世界大恐慌:暗黒の木曜日から始まる悪夢
1920年代、アメリカの好況を支えた住宅や耐久消費財の需要のピークは1926年から1927年に迎えたと言われています。しかし、それにも関わらず株価は上昇を続けバブルさながらの様相を呈していました。
このバブルは1929年10月24日に弾け、ニューヨーク証券取引所の株価暴落(暗黒の木曜日:Black Tuesday)によって崩壊しました。

このアメリカの株価暴落は、国際的な資金の流れにも悪影響を及ぼします。ヨーロッパへの投資拡大のため、アメリカから資金が流入していましたが、証券市場崩壊によって資産が引き上げられていくようになります。

結果、ヨーロッパでは資金流出が続き各国で生産が落ち込むことになり、未曾有の世界大恐慌へに繋がりました。
これに対して、各国は経済への介入を強めていくことになると同時に、保護主義へと走るようになります。
アメリカで起きた証券崩壊はヨーロッパや世界を巻き込む世界大恐慌に
金本位制の崩壊
金本位制は、貨幣の価値が金を基準とした制度です。
金本位制は、貨幣の価値は金が基準となっているため、通貨供給量を人為的調整をすることができません。そのため、経済が管理経済体制で得ることのできる、貨幣の価値をコントロールできるという利点を金本位制では生かすことができなかったのです。

そこで、ヨーロッパ諸国は、1929年の証券暴落をきっかけに金本位制から離脱をしていったのです。
積極的財政政策
金本位制の崩壊とともに、管理通貨体制に入った諸国は、国内への経済介入を深めていきました。
アメリカではニューディール政策、ナチスの経済政策が代表的なものでした。これらは、管理通貨制と金本位制の放棄の採用と表裏一体でした。
ニューディール政策
アメリカでは共和党のフーバー大統領から政権を引き継いだローズベルト大統領によって、市場放任を基軸とした緊縮財政から転換を加えます。

1933年にアメリカは金本位制から離脱します。そして、それに合わせてニューディール政策が行われたのです。目的としては、雇用の創出です。恐慌で失業者が増加しており、それに対応しようとしたのです。

具体的には
- ダム政策によって灌漑を行い、電力を確保するためにテネシー渓谷公社の設置
- 農業調整法(AAA)を1935年に成立させ、農産物市場への介入
- 全国産業復興法(NIRA)によってカルテルの結成を認め労働者雇用の保護(のちに違憲で廃止)
などを行いました。国際貿易秩序では、1934年の互恵通商協定法、35年の中立法によって貿易の活発化を狙いました。
ナチス
1932年に総選挙でナチスが第一党となり、アドルフ・ヒトラーが首相に就任しました。それまで、は予算均衡のために緊縮財政が取られ不況が深刻化しました。

ナチス政権は労働者の政治活動を禁止し、労働協約制度を破壊することで労働者の行動を制限しました。
その一方で、高速道路建設や軍需生産の拡大によって需要拡大をもたらしました。これにより雇用の創出と生産の増加に成功したと言われています。

劇的に失業者は減少しました、その後、経済統制と強化していき、自給自足的な経済体制を進め、軍事部門の強化を行いました。
- 管理通貨体制に入った諸国は、国内への経済介入を深めていきました。
- アメリカではニューディール政策、ナチスの経済政策が代表的
- 国家の経済介入は、管理通貨制と金本位制の放棄の採用と表裏一体
ブロック経済と世界貿易の縮小
これまで説明してきた、金本位制や国家の経済介入は保護主義の動きと連動していました。保護主義とは簡単にいうと、自国に有利な関税引き上げを行う、自由貿易主義とツイをなす考え方です。
世界的関税引き上げのきっかけとなったのは、1930年のアメリカによるスムート=ホーレー関税法です。イギリスも対抗して、32年に関税法を制定しています。
その他諸国も関税引き上げを行い、関税引き上げ戦争の様相を呈してました。こうした状態を止めるためにに1932年にロンドンで世界経済会議が行われました。しかし、交渉は破断し失敗に終わりました。

その後、スターリングブロック、ドルブロックなど自国優先の経済ブロックが形成されることになりました。
結果、こうした経済ブロック化は、ドイツや日本のような資源を持たない国の侵略を引き起こし第二次世界大戦へとつながました。
経済ブロック化は、ドイツや日本のような資源を持たない国の侵略を引き起こすことになってしまい、第二次世界大戦へとつながる
第二次世界体制から戦後へ

世界大恐慌によるブロック経済の進展は、国際間の緊張を高めます。
第二次世界大戦の勃発
第二次世界大戦は1939年9月1日にドイツによるポーランド侵攻し、これに対して、3日にイギリス・フランスがドイツに対して宣戦布告したことで始まります。

主に枢軸国と連合国の対立という構図となっています。枢軸国は、ドイツ・イタリア・日本。連合国は、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、中華民国、オーストラリアなどになります。
第二次世界大戦の戦域は、ヨーロッパ・北アフリカ・西アジアの欧州戦線と、東アジア・東南アジアと太平洋・オセアニア・インド洋・東南アフリカ全域の太平洋戦線に広がりました。

- 第二次世界大戦は1939年9月1日にドイツによるポーランド侵攻
- 枢軸国は、ドイツ・イタリア・日本。連合国は、イギリス、フランス、アメリカ合衆国、中華民国、オーストラリアなど
アメリカ中心の経済秩序の形成
対戦中、ヨーロッパ諸国は軒並み生産が減少します。人口も停滞し一人当たり生産量も減少します。一方で、アメリカ本土は軍需生産によって活況を呈することになります。
アメリカは連合国に対して戦争物資を供与していました。1939年に中立法の改正でイギリスとフランスへの武器輸出を開始し、1941年には武器貸与法を制定して、「その防衛が合衆国防衛にとって死活的」である国々に武器が提供されました。
このような、アメリカの物量によって連合国は当初不利だった戦線を巻き返すことができました。
武器の支援額は500億ドルに達し、イギリスやソ連、中国は恩恵を受けることになります。しかし、その一方でアメリカは経済成長を続け、戦後のアメリカの世界経済秩序の中にヨーロッパを組み込んでいくのでした。
- アメリカは連合国に対して戦争物資を供与していました。
- アメリカの物量によって連合国は当初不利だった戦線を巻き返すことができました。
- 戦後のアメリカの世界経済秩序の中にヨーロッパを組み込んでいくのでした。
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。
また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。
ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。
また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。