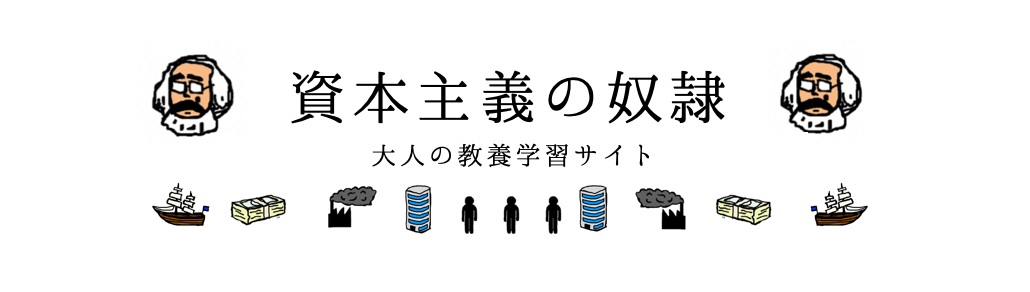1973年に第一次石油危機、1978年には第二次石油危機が起こります。これにより石油の供給不足が起こり、世界中で価格の暴騰が起こります。
これにより国際経済は更なる混乱を迎えることになります。それが、インフレと不景気が同時に起こるスタグフレーションです。
この記事では2つの石油危機の原因とその影響について詳しく解説していきます。また石油危機がおこる前には変動為替相場制への変更(ドル危機)が起こっています。この時期は世界中で危機が連発した時代でした。
また、この記事は以下の書籍を参考に作成しています。西洋経済史をわかりやすくまとめた教科書的な書籍です。よかったら併せて読んでみてください。
石油危機の背景

石油危機は、中東の石油の産油国が石油価格の大幅な引き上げと、石油生産の削減、石油の輸出制限を行ったことで、世界各国で石油が不足し、石油の値段が急激に上昇したできごとです。これにより国際経済は混乱に見舞われることになりました。
2つの石油危機の背景には、主要石油産油国の発言権の増加がありました。1930年代は石油メジャーと呼ばれる国際石油企業が中東原油の採掘権を独占していました。
しかし、中東ナショナリズムの高揚の中で1960年に石油輸出機構(OPEC)を結成し、利益配分の増加を中東側が石油メジャーに対して求めるようになります。そこで採掘料の引き上げなどを実現しています。
こうした背景の延長で、1973年の第一次石油危機と1978年の第二次石油危機によって産油国の発言権は決定的に高まりました。
- 石油危機は、中東の石油の産油国が石油価格の大幅な引き上げと、石油生産の削減、石油の輸出制限を行ったことで、世界各国で石油が不足し、石油の値段が急激に上昇したできごと
- 石油危機の背景には、産油国の発言権は決定的に高まりがあった
第一次石油危機の原因:第四次中東戦争

この石油危機の要因には中東における混乱があります。第一次石油危機の要因には第四次中東戦争があります。
1973年にエジプト軍とシリア軍が南北からイスラエルを攻撃したことで、第4次中東戦争で勃発しました。これにより、イスラエルとエジプト・シリア・サウジアラビアなどのアラブ諸国が対立をするようになります。

この間、サウジアラビアをはじめとするアラブ諸国は、イスラエルに親和的なアメリカやイギリスなどの西欧諸国に対して石油価格を釣り上げて圧力をかけたのです。
第二次石油危機の原因:イラン・イスラーム革命

第二次石油危機では、1978年のイラン・イスラーム革命が要因となっています。
イラン・イスラーム革命は、新米的な王政のもとで近代化を進めていた政府に反発する、ホメイニを中心とする宗教的過激派が国王を追い出した出来事です。これにより、イスラーム共和国が樹立されました。

これにより半欧米的な政権が産油国イランにできたことで、石油の入手が困難になったのです。
- 第一次石油危機の要因には第四次中東戦争があります。
- 第二次石油危機では、1978年のイラン・イスラーム革命が要因
石油危機の影響:スタグフレーションの進行とその後

2度にわたる石油危機は、石油輸入国の供給側のコストを大幅に上げることになります。これにより、スタグフレーションが発生することになります。
スタグフレーションは景気の後退とインフレーションが同時に発生することです。 通常は、インフレーションが起こると景気が拡大すると見られていました。通常インフレは総需要の拡大で起こりますが、スタグフレーションは供給側のコストの増大でインフレが起こったのです。

スタグフレーションは以下の記事で詳細に解説しています。合わせてお読みください。
結果、総需要は変わらない中でインフレが起こるので、取引量が減少してしまいスタグフレーションが起こるのです。
ドル危機と石油危機により景気変動自体が非常に不安定になり、1987年に欧米では暗黒の月曜日という株価暴落も起きています。さらに、日本ではバブルが崩壊します。
しかし、この状態も1990年代には先進国の物価は安定し、むしろ世界的なあデフレが懸念んされるようになっていきました。
- 2度にわたる石油危機は、石油輸入国の供給側のコストを大幅に上げることになります。これにより、スタグフレーションが発生することになります。
- 1990年代には先進国の物価は安定し、むしろ世界的なあデフレが懸念されるようになっていきました。
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。
また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。
ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。
また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。