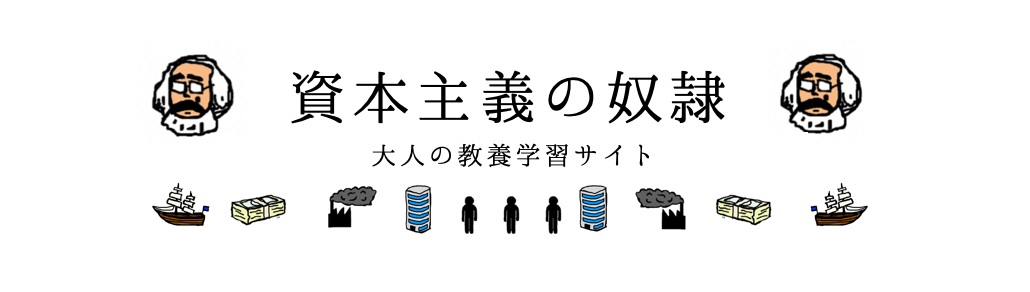この記事では、近世(初期近代)の初期(15世紀〜16世紀)における西洋ヨーロッパの経済史について解説していきます。
また、この記事は以下の書籍をもとに書いた記事になります。非常に西洋経済史の基礎的な部分を解説したものになります。合わせてお読みください。
近世:初期近代の概要

ここでは、15世紀から18世紀までの期間を近世(初期近代)として表現します。ヨーロッパの時代区分としては、
古代→中世→近世→近代→現代
と推移します。もともと、ヨーロッパの伝統的区分では15世紀から現在までを近代と言いました。
近世ヨーロッパの概要
近世ヨーロッパは、中世末期のペストや飢饉などの危機を乗り越え、15世紀末より農業生産が回復し始める時代です。ヨーロッパ各地に特産地が形成され、遠隔地との取引が中世以上に拡大しました。それに伴い、商業・金融制度が発達しました。
また、ヨーロッパは近世には植民地を拡大していました。アメリカ・アジアに植民地が形成されプランテーション農業が発達しました。結果、ヨーロッパ領域を超える国と国を超えた相互関係が生まれるようになったのもこの時代です。
この流れで、イギリス・オランダなど経済的に主導的な役割を果たす国が生ました。これらの国は生産要素(土地・資本・労働)の商品化が進展していくことになりました。一方で、東ヨーロッパではこうした流れは生まれず、東西で経済格差が生まれる原因にもなりました。

近世初期の西洋
- 農業生産が回復
- 植民地の拡大
- 生産要素(土地・資本・労働)の商品化が進展
近世ヨーロッパの国家制度
近世は、中央集権体制に基づく国家形成の動きが生まれた時代です。つまり、現代の国民国家の枠組みの基礎が生まれた時代ということです。
封建制が多くの地域で終焉を迎えました。君主への行政権の集中によって生じた国家(State)が相互に強調対立しながら力学的な関係を維持した。

さらに、国家(State)は、同一言語や習慣などのを有する文化的・社会的まとまりである民族や国家(Nation)を統合していきました。

中央集権化が最も進展したのはイギリスとフランスで、それに対してドイツやイタリアでは国としての分裂状態が続いていました。
- 中央集権体制に基づく国家形成の動きが生まれた時代
- 国家(State)は、同一言語や習慣などのを有する文化的・社会的まとまりである民族や国家(Nation)を統合
近世:初期近代の経済動向の変化

16世紀は、15世紀後半以降の人口増加と生産量の増大によって、経済成長を16世紀以降迎えるようになりました。
特産品の多様化
中世までは、農業は麦類などの限定されたものに限られました。しかし、近世になると、環境・技術・市場の要因から各地から特産品が生まれました。例えば以下のような感じです。
・スペインイギリス中部:牧羊業
・ハンガリー・オランダ北部:牧畜や酪陽業
・プロセイン・ポーランド、北フランス:輸出向け穀物

こうした特産品の多様化は、取引される製品の多様化に繋がっていきました。
商業の変化
特産品の形成や手工業生産の変化は商業にも影響を与えました。
中世では流通ネットワークでは、高級毛織物や東方の香辛料などが地域を超えて運ばれていました。中世末期からは、穀物や木材などの「重量財」や安価な織物などの日用品が地域を超えて流通しました。

例えば、バルト海貿易ではドイツ騎士団領やポーランドからの穀物の西方への輸出が増加したことが挙げられます。
これらは流通品目の多様化は
・輸送コストの低下
・地域間の価格差
に基づく遠距離貿易を促進しました。地域間の価格差の減少は、のちに説明する16世紀のアントウェルペン、17世紀のアムステルダムの取引所が大きな役割を果たしました。
- 環境・技術・市場の要因から各地から特産品が生まれました。
- 穀物や木材などの「重量財」や安価な織物などの日用品が地域を超えて流通
大航海時代におけるヨーロッパの植民地拡大

近世初期からヨーロッパは大航海時代に突入します。大航海時代とはヨーロッパ諸国がアフリカ・アジア・アメリカ大陸への大規模な航海が行われた時代のことです。
これにより、ヨーロッパ諸国は植民地を獲得することになります。またこれにより価格革命が起こり、ヨーロッパは大きく経済成長を遂げました。
ここでは
- レコンキスタ
- インド航路の開拓
- アメリカ大陸の開拓
- 世界周航
とそれによる価格革命について解説していきます。
中世のヨーロッパ:植民地の拡大レコンキスタ
大航海時代が始まる為には、ヨーロッパが大西洋に手が伸びる必要性がありありました。そこで重要になった出来事がレコンキスタです
レコンキスタ(国土回復運動)とは、718年から1492年までに行われた、複数のキリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動の総称です。レコンキスタは1492年のスペイン王国が最後のイスラーム勢力を駆逐 することで完了します。
レコンキスタの背景にはイベリア半島がイスラームによって制服されていたことがありました。
7世紀にアラビア半島で成立したイスラームは北アフリカに広がり、8世紀にはジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島に達しました。
西ゴート王国がウマイヤ朝によって711年に滅ぼされると、以降7世紀に渡って、イベリア半島はキリスト教世界とイスラーム世界が対立する地域となりました。

732年のトゥール・ポワイエ間の戦いに勝利したフランク王国によってイスラームの侵入は食い止められた。

13世紀に入ると、半島の大半がキリスト教勢力の手に落ちました。1479年にはアラゴン王国のフェルナンドとカスティーリャ王国のイザベルの結婚によってスペイン王国が成立し、1492年には最後のイスラム範囲が残ったグラナダを陥落させ、レコンキスタが終了しました。

レコンキスタ(国土回復運動)とは、718年から1492年までに行われた、複数のキリスト教国家によるイベリア半島の再征服活動の総称
インド航路の開拓:ポルトガル
オスマン帝国の台頭
ポルトガルによって、アフリカ経由のインド航路が開拓されました。その背景にはオスマン帝国の台頭がありました。
15世紀にはヨーロッパの東部で、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルがオスマン帝国によって陥落させられています(1453年)。
それにより、ヴェネチアやジェノヴァといったイタリアの諸都市の繁栄の基盤であった地中海経由の東方貿易が収縮しました。こうした中で、ポルトガルは地中海経由に変わる交易路の開拓の必要性に迫られます。

結果、喜望峰の発見はヨーロッパ経済の重心を地中海から大西洋へ移すことになります。
ポルトガルによるアフリカ探索
大航海時代は、ポルトガルによるアフリカ探索から始まります。
ポルトガルは、イベリア半島北西部に位置し、レコンキスタの拠点となったレオン王国のポルトゥカーレ伯領を起源とします。12世紀に王国になり、13世紀までは現在とほぼ同様の国土を持つに至ります。そして、カトリック国としての地位を確立していきました。
このポルトガル探索の中心となったのがエンリケ航海王子でした。

ジョアン1世の第5子として生まれたエンリケは、1414年にセウタ攻略戦に参加した際に、イスラーム社会の中に孤立するキリスト教国家の伝説(プレスタージョンの伝説)やサハラ砂漠を横断する隊商について知ることになります。
これをきっかけに、アフリカ西岸の探索が始まります。アフリカ西岸の探検は、イスラームに支配される北アフリカを迂回してアフリカの菌や象牙、奴隷といった財にアクセスするという経済的動機もありました。
ポルトガル南部のアルガルヴェ地方の総督になったエンリケは、そこを拠点にマディラ地方を発見しましう。1427年にはアゾレス諸島を発見し植民地化。
これにより砂糖やワイン占領、小麦などが手に入るようになりました。
1434年にはエンリケの部下ジウ・エアネスがブジュドゥール岬を越えて無事に帰還しました。1456年にはアフリカ西端のカーボベルテ諸島を発見し、サハラ砂漠の南端に達した。

これによりイスラームの対象に頼ることなく、金やその他の奢侈品と奴隷が直接ポルトガルに持ち込まれるようになりました。
インド航路の発見
1460年にエンリケ航海王子がなくなった後も、ポルトガルによるアフリカ探索は進みます。
1488年に、バルトロメウ・ディアスは、アフリカ南端の喜望峰に達して、大西洋からインド洋への航海が可能であることを示しました。
マヌエル1世の名を受けて、1497年にリスボンを出港したヴァスコ・ダガマは喜望峰を越えてヨーロッパ人には未知の存在であったアフリカ東岸の北上を開始します。

1498年にはマリンディに到達し、ここで初めてインド人商人と邂逅した。その後、インド洋の横断を試み、現地人の水先案内人イブン・マージドとともに、インド洋を横断を成功させました。
1498年にはインド南西部のカリカットに到達し、喜望峰ルートで香辛料がポルトガルにもたらされることになりました。
16世紀に入るとアフリカ東岸のモザンビークに要塞を築き、1509年にディウ沖の海戦でマクムール朝エジプト・オスマン・グラジャラートの連合軍を破って、インド洋の制海権を手中に納めました。
1510年にはゴアを占領して、アジアにおけるポルトガルの活動拠点となりました。1515年にはペルシャ湾のホルムズ島の征服が行われます。
その後もポルトガルは、貿易拠点を拡大して、香料諸島やセイロンのコロンボなどに要塞を建設しました。日本とも1543年の種子島漂着から1639年の江戸幕府による来航禁止まで貿易が続いた。中国とも16世紀諸島から断続的な関係を続けていました。

ポルトガルの植民地は、アフリカ東西両岸の沿岸諸都市、ペルシャ湾の入り口にあたるホルムズ、インド亜大陸西岸の中部に位置するゴア、マレー半島からマラッカ海峡を睨むマラッカ、中国南東部のマカオと、通商上の要地に鎖状に築かれた要塞とそれを結ぶシーレーンからなっていたと考えてよい。
そのため、「海上帝国」と呼ばれることもある。
- ヴァスコ・ダガマは喜望峰を越えてヨーロッパ人には未知の存在であったアフリカ東岸の北上を開始します。
- 喜望峰ルートで香辛料がポルトガルにもたらされることになりました。
アメリカ大陸の発見:コロンブス
スペイン王国の女王イサベルの許可を得たクリストファー・コロンブスは、サンタマリア号をはじめとする三隻で、西回りインド航路の探索のためにスペイン南西部のパロスを出港しました。彼はアメリカ大陸を発見した人物です。

1402年に発見されていたカナリア諸島に寄港して食料などを積み込んだあと、大西洋を西進して10月にサンサルバトル島に辿り着きました。
キューバ島とイスパニョーラ島の探検の後、帰国の途につき、1493 年にスペインに帰国し熱狂的な歓迎を受けました。その後、コロンブスは4度もの航海に出かけています。

1493年にコロンブスが帰国は、ポルトガルとスペインの間の緊張を走らせました。結果、1494年に教皇アレクサンデル6世の承認によって決められたトリデリシャス条約によってこの問題は解決されました。
クリストファー・コロンブスは、アメリカ大陸を発見した人物
コロンブスののちに、ポルトガル側でもアメリカ大陸を開拓しました。1500年にリスボンを出港したカブラルは、カーボベルテから喜望峰へ向かう途中、偶然ブラジルを発見しました。
カーボベルでから西370レグアの地から南北に引いた線より西側で発見された土地はスペイン領、東側で発見された土地はポルトガル領と定められました・
マゼランの世界周航
1519年にはマゼランが世界周航に出港します。ポルトガルの下級貴族の家に生まれたマゼランは、操船技術に秀でた人物でした。そして西回り航路で世界一周を初めて達成した人物でもあります。

その後、スペインのカルロス1世に西回り航路の計画を伝え、財政的援助を受けて、トリニーダ号、ヴィクトリア号をはじめとする5隻の艦隊でセビリアを出港しました。
出港当時は、ラプラタ川の河口が太平洋への入り口だと考えられていたが、入念な調査の結果、それが河川であることが判明し、マゼラン一行はさらに南下を続けることになります。
1520年でサンフリアンで越冬したマゼランは、10月に現在のマゼラン海峡に侵入し、11月に南太平洋に出て、ついに西回り航路を発見しました。
その後の太平洋横断はさらに苦難が続き、ほぼ三ヶ月かけて太平洋を横断し、1521年にマリアナ諸島に到達しました。その後、フィリピンに到達した際に、マゼランは現地人との戦闘で死亡し、1522年に希望峰経由でスペインにたどり着いたのはエルカーの率いるヴィクトリア号だけでした。

スペインは海外植民地で領域支配を行いました。
マゼランが死去したのと同じ1521年には、現在のメキシコ周辺にあったアステカ王国がエルナン・コステルによって滅ぼされている。

また、1534年にはフランシスコ・ピサロによってインカ帝国が滅ぼされている。ポルトガル領を除く南米大陸のほぼ全域がスペインの植民地になった。

1519年にはマゼランが世界周航に出港します。ポルトガルの下級貴族の家に生まれたマゼランは、操船技術に秀でた人物でした。そして西回り航路で世界一周を初めて達成した人物でもあります。
価格革命
15世紀後半から17世紀初頭にかけてのヨーロッパでは、のちに「価格革命」と呼ばれる長期的な趨勢としての価格上昇が見られました。
農産物・土地等の価格上昇率が工業製品・賃金に比べて高いことなど、商品によって価格上昇率が異なるのも価格革命の特徴です。
価格革命の要因として、新大陸からの金銀の流入が増加が挙げられます。それ加えて、南ドイツ銀鉱山における技術革新も大きな影響を与えたとされます。
15世紀後半から17世紀初頭にかけてのヨーロッパでは、のちに「価格革命」と呼ばれる長期的な趨勢としての価格上昇が見られました。
近世ヨーロッパにおける経済の拡大

近世初期は、アントウェルペンにおいて金融制度が発達した時期でもありました。そのため、アントウェルペンが経済の中心隣ヨーロッパを牽引していました。
また、それにより中世に経済の中心であったイタリアが没落した時代でもありました。
アントウェルペンは大市が開催れていたが、人口5000人のブラハントの小都市に過ぎませんでした。しかし、15世紀以降急激に発展を見せた。
アントウェルペンは、他地域に比べて自由に経済活動ができました。
1531年に建設された新取引所には「すべての国と言語の商人のために」と書かれていタコとからもわかります。イギリスやドイツ、イタリア、スペイン、ポルトガルなどから外国商人が集まりました。
取引所が設立の背景には遠隔地商業の拡大がありました。
取引所で公示される価格が公式なものとされ、商品売買が行われるようになりました。これにより地域間の価格差が低下したのです。
最終地の市場での売却価格が不明であることの差損のリスクが低下する。周辺の地域の価格形成機能が低下していった”
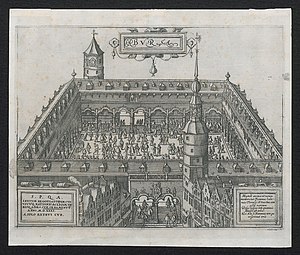
アントウェルペンが隆盛した要因には
- ライン川流域と北中部低地地域の地域内流通
- ヨーロッパ諸国・諸地域
との貿易が集中したことが挙げられます。
例えば、バルト海交易のハンザからの穀物輸入、イギリスからの羊毛・半加工毛織物の輸入、南ドイツからの銀銅の輸入が挙げられます。
スペイン、ポルトガルを介した植民地との貿易の拠点となり、香辛料やアメリカ新大陸の銀が扱われました。16世紀には人口10万人になっています。

また、アントウェルペンでは手形が第三者にも譲渡できるようになりました。この手形が新取引所では手形決済が行われるようになります。
1520年以後にはハプスブルク家の公債をめぐる交渉のために皇帝の代理人が常駐し、南ドイツのフッガー家も支店を設置して多額の公債が取引される金融市場となりました。
アントウェルペンが経済の中心隣ヨーロッパを牽引していました。
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。
また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。
ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。
また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。