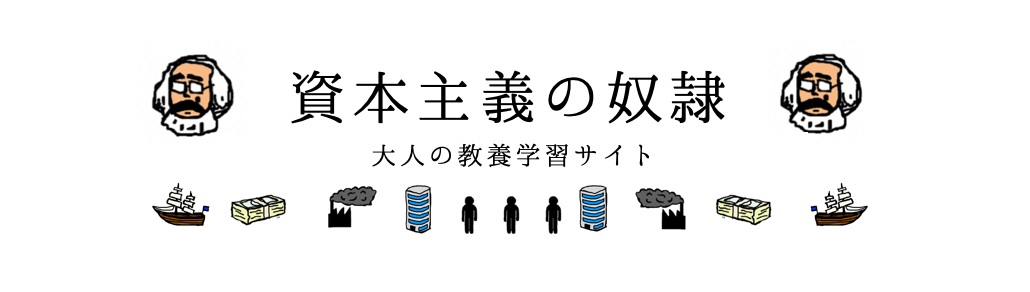この記事では、近世(初期近代)の後期(17世紀〜18世紀)における西洋ヨーロッパの経済史について解説していきます。
この時期は、のちに始まる産業革命などの人類の発展を準備した時期でもありました。
また、この記事は以下の書籍をもとに書いた記事になります。非常に西洋経済史の基礎的な部分を解説したものになります。合わせてお読みください。
近世:初期近代の概要

ここでは、15世紀から18世紀までの期間を近世(初期近代)として表現します。ヨーロッパの時代区分としては、
古代→中世→近世→近代→現代
と推移します。もともと、ヨーロッパの伝統的区分では15世紀から現在までを近代と言いました。
近世ヨーロッパの概要
近世ヨーロッパは、中世末期のペストや飢饉などの危機を乗り越え、15世紀末より農業生産が回復し始める時代です。ヨーロッパ各地に特産地が形成され、遠隔地との取引が中世以上に拡大しました。それに伴い、商業・金融制度が発達しました。
また、ヨーロッパは近世には植民地を拡大していました。アメリカ・アジアに植民地が形成されプランテーション農業が発達しました。結果、ヨーロッパ領域を超える国と国を超えた相互関係が生まれるようになったのもこの時代です。
この流れで、イギリス・オランダなど経済的に主導的な役割を果たす国が生ました。これらの国は生産要素(土地・資本・労働)の商品化が進展していくことになりました。一方で、東ヨーロッパではこうした流れは生まれず、東西で経済格差が生まれる原因にもなりました。

近世の西洋
- 農業生産が回復
- 植民地の拡大
- 生産要素(土地・資本・労働)の商品化が進展
近世ヨーロッパの国家制度
近世は、中央集権体制に基づく国家形成の動きが生まれた時代です。つまり、現代の国民国家の枠組みの基礎が生まれた時代ということです。
封建制が多くの地域で終焉を迎えました。君主への行政権の集中によって生じた国家(State)が相互に強調対立しながら力学的な関係を維持した。

さらに、国家(State)は、同一言語や習慣などのを有する文化的・社会的まとまりである民族や国家(Nation)を統合していきました。

その中で、中央集権化が最も進展したのはイギリスとフランスで、それに対してドイツやイタリアでは国としての分裂状態が続いていました。
- 中央集権体制に基づく国家形成の動きが生まれた時代
- 国家(State)は、同一言語や習慣などのを有する文化的・社会的まとまりである民族や国家(Nation)を統合
近世後期の概要:17世紀の危機

ここでは近世後期の概要について解説します。
17世紀の危機
近世後期は17世紀の危機と言われるように、戦争や経済成長の停滞などによってヨーロッパ自体が停滞していた時代でした。
近世初期まではのヨーロッパは、大航海時代により、新大陸からの金銀が大量にもたらされました。それにより、商工業の発展や農業生産量の増加に人口増加とそれによる経済発展を遂げました。
しかし、17世紀からは、
・新大陸の銀の産出が減少し、銀の流入量が減少
・天候不順による人口の減少
しました。これにより経済成長は停滞し、各国の経済格差が拡大しました。

その中で、オランダやイギリスは経済の中心を担うようになりました。一方で東欧諸国は経済的に停滞することになりました。
◆17世紀の危機
- 17世紀のヨーロッパは経済成長は停滞し、各国の経済格差が拡大
- オランダやイギリスは経済の中心を担うようになりました。一方で東欧諸国は経済的に停滞することになりました。
国境の確定:30年戦争
近世後期は現在に近いヨーロッパの国境が確定した時期でもありました。その契機として宗教改革を契機とする三十年戦争がありました。
宗教改革は16世紀の前半、ドイツのルターやカルヴァン派によって始まりました。彼らは、既存のカトリック教会の腐敗を批判しました。これに賛同するカトリック派閥の人々がヨーロッパ各国に現れました。
これにより、ヨーロッパはキリスト教世界はカトリック教会とプロテスタントに二分されました。この動きは各国の経済にも大きな影響を与えました。

カトリックとプロテスタンの対立は広範囲な宗教戦争に転化し、三十年戦争(1618〜1648年)というヨーロッパ全土に渡る戦争が勃発しました。この戦争は、宗教的な意味だけでなく国家間の覇権の奪い合いという側面もありました。
1648年に三十年戦争はウェストファリア会議で終結をむかえました。この条約は、世界最初の近代的な国際条約で、現在のヨーロッパに近い国境が確定した条約でもありました。

続いて、この時期のオランダ、イギリス、フランス、ドイツの17世紀の状況を見ていきましょう。
近世後期は現在に近いヨーロッパの国境が確定した時期、宗教改革を契機とする三十年戦争によって国境が確定した
オランダの台頭:金融の中心アムステルダム

オランダは、17世紀に黄金時代を迎えました。その要素には2つあります。
1つ目は、ポルトガルに変わりアジア貿易を支配するようになったこと。
2つ目は、アムステルダムがヨーロッパの国際貿易・金融の中心となったこと
が挙げられます。これらについてオランダの成立と合わせて解説していきます。
オランダ独立戦争
オランダ独立戦争(八十年戦争)は、1568年に始まり、最終的には1648年のオランダ独立までの80年にわたって続けられた戦争のことを指します。
きっかけはスペイン王のフェリペ2世が父カール5世から低地地方を引き継いだことから始まりました。

フェリペ二世は財政危機を乗り越えるために課税をやカトリック教会の強化をしました。これに対して低地地方の住民たちは反発しました。
結果として、低地地方の南部諸州はスペインの手に落ちました。しかし、北部7州はユトレヒト同盟を組んで抵抗し、イギリスとフランスの承認を受けて16世紀末には実質的にオランダとしての独立を果たしました。

スペインが承認したのは1648年のウェストファリア条約によってです。
アムステルダム:金融・商業の中心へ
独立後のオランダは、黄金時代をむかえます。
オランダ商業は、
- バルト海交易
- アジア諸地域
- カリブ海の植民地
から運ばれてくる産品をヨーロッパ各地に運びました。
バルト海貿易では穀物や木材という東欧や北欧の産品を東から西へ、毛織物などの西欧の産品や植民地産品を西から東へ運びました。

この拠点としてアムステルダムは、16世紀のアントウェルペンを受け継ぐ貿易と金融の中心となりました。
アムステルダム銀行・アムルテルダム取引所
金融の中心の象徴として、1609年に設立されたアムステルダム銀行があります。手形振替業務を主要業務としていました。これにより同行の口座振替が貿易決済に用いられました。安全性と利便性に定評があり、オランダ商人の貿易による優位性を他kめました。

1611年にはアムステルダム取引所が設立されます。ここでは貿易で持ち込まれる産品だけでなく、政府債や東インド会社の株式も取引対象となっていました。

取引所での価格の情報は、当時多く発行された新聞を通してヨーロッパ全域に伝えられました。そして、アムステルダムは世界の取引の指標となる、価格を示す役割を果たしたのでした。
開かれた社会
オランダは成立当初から、各国からの移民を受け入れました。ヨーロッパ各地の商人はオランダ国籍を取得し、オランダ商業の人的ネットワークも築かれました。
また、宗教上の信仰に対してもも寛容で、カルヴァン派が最も優位でしたが、カトリックやユダヤに対しても開かれていました。
この開かれた社会であることがオランダを金融の中心に成らしめた理由の1つとも言えます。
開かれた社会であることがオランダを金融の中心に成らしめた理由
アジア植民地経営:オランダ東インド会社
オランダ独立戦争の間、オランダが1602年に設立したオランダ東インド会社は、インドから東南アジアにかけての一帯に進出します。

東インド会社は、世界初の株式会社と言われており、その株式はアムステルダム取引所でも販売されました。
その後の、オランダの植民地経営の最も重要な柱となりましたした。オランダはポルトガルに変わり、インド洋や東南アジア地域に植民地を広げ覇権を握るようになります。
拠点はバタヴィアに設けられました。
東インド会社は、香料諸島における香料や、絹織物、中国陶器をヨーロッパに輸入する役割を果たしました。
それだけでなくアジア諸地域間の貿易にも積極的に参加し、長崎出島とマカオ、バタヴィアを結ぶ東シナ海での三角貿易も行いました。
また、インドネシアのプランテーション経営を行い、ヨーロッパの需要動向に合わせて出荷をすることで安定した利益を獲得していました。

これらの貿易を担った商人は、コープマンを呼ばれ、貿易に必要な信用・情報・資産を所有してました。彼らは国家と結びつくとともに、貴族との婚姻によって商取引上の優位性を占めました。
東インド会社は、世界初の株式会社と言われており、その株式はアムステルダム取引所でも販売されました。
アメリカ大陸の植民地経営:オランダ西インド会社
オランダは、アジアに限らずアメリカ大陸にも手を広げようとしました。
その担い手は1621年に設立された西インド会社でした。カリブ海地域での植民地獲得を目指しました。
しかし、この地域はスペインやイギリス、フランスという競合がひしめいており十分な成果を上げることができませんでした。
結果として、アフリカとラテンアメリカを結ぶ奴隷貿易を主要業務に切り替えました。
イギリスの経済成長の展開:農業革命と海外貿易の拡大

イギリスは、他のヨーロッパ諸国と比較して中央集権が進んでいました。しかし17世紀中盤から後半にかけて怒ったイギリス革命によって絶対王政が倒され、立憲君主体制が成立しました。
17世紀のイギリスは
- 土地所有構造の変化
- 農業生産量の増加
- 植民地の開拓
が起こり、経済を成長させることに成功し、のちの産業革命の中心地となりました。
また、オランダの衰退後は18世紀頃からはロンドンが金融商業の中心地として機能するようになりました。
デューダー朝による絶対王政
イギリスが中央集権化の傾向が強まったのは、デューダー朝のヘンリー7世(1485年〜1509年在位)以降のことです。

ヘンリー7世は1487年の星室裁判所法という法律を作ることで、地方貴族の反乱などを抑制したと言われています。
その後、ヘンリー8世は、結婚に関することでローマ教皇と対立します。そこで、彼は、国王至上法という法律を1534年に成立させることで、ローマ・カトリック教会から離脱し、イギリスのカトリック教を独立イギリス国王が頂点のものとして作り替えました(イギリス国教会)。
イギリス国内には教皇を頂点として、修道院がいくつも国内に存在していました。しかし国王至上法などによって、イギリス国王が頂点として修道院などが従属するようになったのです。
その後、1530年代に、修道院を解散させる法律制定させ、修道院領を手に入れました。修道院領は、のちに貴族やジェントリーなどに売却され、中流貴族であるジェントリーを豊かにしました。
イギリス革命(ピューリタン革命・名誉革命)
イギリスの君主を頂点とする体制は、17世紀におこったイギリス革命によって変革されます。
イギリス革命は
- 1642年のピューリタン革命
- 1688年の名誉革命
に分けることができます。
革命の背景には17世紀の危機による経済の停滞による行き詰まりなどがありました。イギリス革命、特に名誉革命ののちはジェントリーを中心に農業革命が起こり飛躍的に農業生産量が増加しました。
ピューリタン革命は議会派と王党派の対立から始まりました。議会派は、先のピューリタンのジェントリーを中心とした党でクロムウェルが指導権を握りました。

この背景にはスチュアート朝のジェームズ1世のピューリタンへの弾圧がありました。この結果、議会派が勝利し共和制へとイギリスは移行しました。
しかし、クロムウェルが独裁体制を敷き苛烈な政治を行いました。彼の死後は、その反動から1660年にスチュアート朝のチャールズ2世が王政復古を果たします。

これに対して反発をした議会は、1688年にチャールズ2世の排除を議会ははかり、オランダからウィレムという王様を迎え入れました。結果チャールズ2世は亡命しました。
1689年、議会は権利の章典を公布して、立憲君主政を実現させました。これが名誉革命です。

イギリス革命は、経済の停滞や人口減少といった経済の行き詰まりがありました。結果、立件民主制によって王の恣意的な課税が制限されることになりました。
さらに、議会の中心を占めていたのが地主階級が多く、これがのちのイギリスの農業革命につながっていきます。
イギリス革命は、イギリスを絶対王政から立憲民主制へと移行させた
経済成長:農業革命
イギリスの農産物供給は18世紀になると大幅に増加します。これを農業革命と言います。
人口も1680年代以降から漸増傾向にありましたが、18世紀から加速しました。この人口増加を満たすレベルでの農業生産量の供給を実現しました。その要因には、囲い込みが挙げられます。
囲い込みとは中世頃までは、所有権が曖昧で細かく分割されていた土地の所有権を明確にすることです。これにより土地の経営規模が大型化しました。囲い混みが起こる前までは、住民全員が使える共同所有地があったのです。

これにより、生産の効率化が起こり必要な投下労働量を大幅に減少させました。
しかし、囲い込みによって、共有地が失われたことで貧窮する農民が出たのも事実です。こうした人々は労働者として都市に流入しました。
農業革命:イギリスの農産物供給は18世紀になると大幅に増加します。これを農業革命
海外進出の拡大
17世紀からはイギリスは、ヴァージニア植民地などの北米植民地へと進出していました。
北米からは、タバコや砂糖などをイギリス本国へ輸出していました。これらの商品をヨーロッパ諸国へさらに輸出することで、莫大な利益をイギリス本国は得ていました。
また、これにより北米植民地も購買力を拡大させ、イギリスの製造業に市場を与えました。これにより、イギリス国内では非農業人口が増加しました。
そのほかに、カリブ海植民地では奴隷を使用した綿花のプランテーションを展開しました。その結果、綿花を受け入れる港としてリバプールがロンドンに次ぐ都市として発展を遂げました。

金融の中心ロンドンへ
海外貿易の進展は、イギリスの金融商業の中心地としての役割を増大させました。
1694年に設立されたイングランド銀行は、海外進出の経済的主体である東インド会社や南海会社と並んで公債を引き受けました。これにより、政府の財政支出を支えました。

17世紀後半には、東インド会社や南海会社などの株式を取り扱う専門の証券業者が現れました。彼らはシティのコーヒーハウスに集まり、情報交換や取引を行いました。
ちなみにコーヒーハウスは1773年に証券取引所と名を改めました。1802年には正式にロンドン取引所になっています。

- 17世紀からはイギリスは、ヴァージニア植民地などの北米植民地へと進出
- 海外貿易の進展は、イギリスの金融商業の中心地としての役割を増大させました。
フランスにおける重商主義:ブルボン朝

フランスでは絶対王政が繰り広げられました。そのため、立憲民主制を軸としたイギリスと比較して経済成長が遅れたと指摘されることもあります。
この章では、
- ブルボン朝の絶対王政
- 重商主義
について解説します。
ブルボン朝の成立
ブルボン朝はアンリ4世から始まりました。ブルボン朝はルイ13世、ルイ14世、ルイ15世、ルイ16世からフランス革命でルイ16世が処刑されるまでの200年にわたって存続した王朝です。
特にフロンドの乱(1648~1653年)は、ブルボン朝の中央集権体制を確固たるものにしました。この乱は、ルイ14世治世期の宰相 J.マザランへの反感を背景に勃発しました。

新旧官僚の対立と貴族の思惑が交錯したこと。そして中央集権化に対する民衆の反感によって、パリを中心にフランス全土を覆う内戦になりました。


結果、マゼランは民衆の反乱を鎮圧することで決着を見ます。この出来事は、ブルボン朝の支配体制を確立する契機となりました。
フロンドの乱によって地方勢力が制圧されフランス王国は絶対王政が確立した。
フランスの財政状況:公債発行の状態化
ブルボン朝は多くの対外戦争に参加しており、戦費は莫大なものになりました。これにより、増税に加えて公債の発行で財源をまかなうことになりました。
例えば、三十年戦争への介入。ルイ14世の時にはファルツ継承戦争(1688〜1697年)、スペイン継承戦争(1701ね〜1713年)。ルイ15世の時になh、オーストリア継承戦争(1740〜1748年)、七年戦争(1756年〜1763年)がなされました。三十年戦争ではアルザスやロレーヌを手に入れています。
これは領土獲得を目指したもので、獲得した領土によって半永久的に獲得できる歳入を目的としていました。
この結果、ルイ14世治世下の財務総監コルベールは税収増加を目的に重商主義を推進しました。
コルベール主義:重商主義
重商主義は、マザランの死後に財政を担ったコルベールによって推進されました。重商主義とは
- 輸出産業奨励
- 輸入品への関税
- 輸入代替
- 1664年設立のフランス東インド会社による植民地経営
を軸として行われました。こうした政策の問題点として、保護主義政策によって貿易そのものを阻害すること、特定国内産業の推進による他産業へのダメージがありました。
また、重商主義はコルベールが推進したこともあり、コルベール主義との別名もありました。
これに対して、ケネーらフランスの重農主義の経済思想家は反対を示しました。
重農主義とは国の富を農業生産物であるとしておりました。そのため、輸出産業という農業以外の産業を優遇する政策には反対だったのです。

一方で重商主義は、国の富を金と捉えていました。そのため、輸出によって金を蓄積しようと考えたのです。

これらの対立を、理論家したのがアダムスミスでした。これらの理論をさらにまとめ自由放任主義を唱えました。アダムスミスの記事は別の記事で解説していますので合わせてお読みください。
重商主義は、国の富を金と捉えていました。そのため、輸出によって金を蓄積しようと考えたのです。
神聖ローマ帝国の没落とプロセイン王国の隆盛

神聖ローマ帝国
神聖ローマ帝国の始まりは、962年に東フランク王国のオットーが、ローマ教皇からローマ帝国皇帝の冠を授けられた(オットーの戴冠)を契機として生まれた帝国です。(神聖ローマ帝国という国名が正式下するのは12世紀のこと)

最盛期にはフランスとイギリスを除くヨーロッパ全域を支配するまでになりました。この時期は、ハプスブルク家が皇帝の地位を独占していた時期になります。この時期は別名ハプスブルク帝国とも呼ばれます。

この中で、プロセインやハプスブルク帝国が力を持ち始めるようになります。
三十年戦争を契機とする衰退
しかし、三十年戦争になると神聖ローマ帝国は影響力をほとんど失うようになります。ドイツ圏が主に戦場になったため、この地域の経済的発展は阻害されました。
ウェストファリア条約の締結によって、神聖ローマ帝国の皇帝の権限の低下が定められました。これにより神聖ローマ帝国は実質上分裂を余儀なくされました。こうした状況は19世紀まで続きました。

特に東欧や中欧、例えばプロセインやハプスブルク帝国などはその例に上がります。
また、経済においては農業と商業ともに進展を遂げていた側面もありました。
中世末期から形成されてきた領主制が、17世紀から強化されるようになりました。三十年戦争によって窮乏していた農民は、これらの領主のもとに駆け込むようになります。結果として農民の農奴化(再版農奴制)や賦役の強化が進むようになりました。

結果として集約的な農業か可能になり農業生産量が増加したのです。
また、プロセインではのちに説明する選帝侯フリードリッヒ・ヴィルヘルムが、フランスなどから逃げてきたユグノーなどを招き入れることで商業が発展しました。
農民の農奴化(再版農奴制)や賦役の強化が進むようになりました。集約的な農業か可能になり農業生産量が増加したのです。
プロセイン王国の台頭

神聖ローマ帝国以外に、ヨーロッパに影響を与えたのがプロセインです。

ちなみにプロセインはドイツ人の東方植民の一環として移住して来たドイツ騎士団が定着したことがきっかけとして生まれた国家です。
三十年戦争に参戦していた選帝侯フリードリヒ=ヴィルヘルム(1640年〜1688年)は、プロセイン公国(ブランデンブルク)の常備軍の建設を軸に国力の充実を図っていきました。

彼の孫のフリードリッヒ3世の治世下で、1701年にプロセインは公国から王国へと昇格します。これによりプロセインの王フリードリッヒ・ヴィルヘルム1世(フリードリッヒ3世と同じ人物:1688年〜1740年)がここに誕生します。

彼は軍隊王と呼ばれました。その名の通り、彼は財政改革と国家官僚制の整備を進め、独特の軍国主義を展開しました。

子のフリードリッヒ2世(1740〜1786年在位)も、父の常備軍を活用してはプルブルク帝国と対立を重ねながら、最終的に列強の仲間入りを果たすまでになりました。
国内では重商主義的な産業振興と農民保護を進め、西欧的な法制の整備と国家官僚制の強化に努めました。
プロセインでは、フロードリッヒ・ヴィルヘルムを中心に、重商主義的な産業振興と農民保護を進め、西欧的な法制の整備と国家官僚制の強化に努めました。
ハプスブルク帝国の改革

ハプスブルク帝国は、18世紀に入りオーストリア継承戦争(1740〜1748年)や七年戦争(1756〜1763年)にプロセイン王国と対決し苦戦をしいられました。
この結果、マリア・テレジア(在位1740〜80年)を中心に老地区下した国家制度を改革をしていくようになります。主に中央集権制の強化を目的とした改革でした。
1つが徴兵制の施行による常備軍の強化、2つが国家財政の整備でした。
共同統治者であり後継者でもあった、ヨーゼフ二世も啓蒙専制君主の代表と言われるように改革を進めます。
この政策としては貴族や教会などの大土地所有者を抑え込み、マリアテレジアの中央集権強化を目的としたものになります。

たとえば、農民解放やユダヤ人に対する寛容令、農奴制や賦役の廃止による大土地所有者の切り崩しになります。
しかし、これらの改革は領主層や大土地所有者の反対にあい、結局貫徹されることなく終わりました。
マリア・テレジアとヨーゼフ二世は、中央集権化を進めるが、結局失敗に終わる
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。
また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。
ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。
また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。