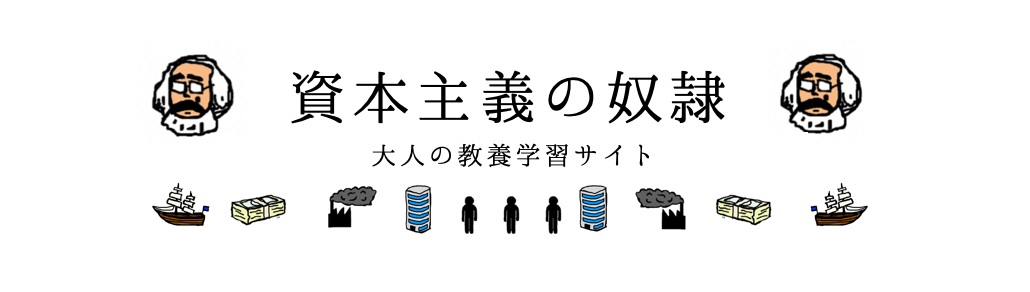この記事では、ナポレオン戦争について解説します。ナポレオン戦争は、ウィーン体制という現代ヨーロッパの基礎とも言える政治体制を作りました。
さらに、ドイツの経済的統合を進めたため、第二次産業革命が起こる遠因ともなりました。
ナポレオン戦争とは?

ナポレオン戦争とは、1796〜1815年の間に、ナポレオン・ボナパルトによって繰り広げられた一連の戦争です。
ナポレオン戦争は、ウィーン体制成立のきっかけとなり、現在のヨーロッパ秩序を作り出すきかっけになりました。

ナポレオン戦争の推移

ナポレオン戦争は、当初フランス革命に対する諸外国の干渉から、フランスを守る防衛戦争として始まりました。しかし、その後
ナポレオンの台頭
フランス革命の最中、オーストリアとイギリスが干渉戦争を仕掛けてきたことから始まります。
1793年にイギリス、オーストリア、プロイセン、スペインなどによって第一次対仏大同盟が結成され、フランスに戦争を仕掛けてきたのです。

それに対してナポレオンは防衛戦争の指揮を取る中で台頭してきます。1796年にナポレオン戦争が勃発し、ナポレオンは26歳の時にオーストリアを撃破します。

フランスに戻ったナポレオンは、1799年11月9日にブリュメール18日のクーデタを起こします。
そこで、第一統領になり、独裁政権をフランスにおける実験を握りました。
征服戦争
フランスの市民から支持を得たナポレオンは、防衛戦争から一転して侵略戦争を始めます。
まず、1800年、ナポレオンは反撃のためアルプス山脈を越えて北イタリアに進出。6月14日のマレンゴの戦いでは、オーストリア軍の急襲を受けたが撃破します。同年にもホーエンリンデンの戦いでオーストリア軍を撃破しました。
1804年にナポレオンが皇帝に即位したことで、第3回対仏大同盟が結成されました。対抗してイギリス本土上陸を目指しトラファルガーの海戦を行いましたが、イギリス海軍に敗北しました。

ですが、ナポレオンは陸上戦では連勝を重ねました。
1805年にアウステルリッツの戦いでオーストリア・ロシア軍、1806年にイエナの戦いでプロイセン軍に勝利ました。また、1807年にポルトガル征服、1808年にスペイン征服を行いました。
ナポレオン戦争では、1812年段階でナポレオン1世がヨーロッパのほぼ全ての領域を影響下に置きました。

ナポレオンの没落
この中で、ナポレオンは大陸封鎖令を出します。これは、イギリスとの貿易をフランスの影響下にある国に禁止する法令です。
結果、イギリスも経済的に苦しくなりますが、フランス影響下の国々も困窮化することになります。しかし、ロシアはイギリスと貿易を継続しました。
それに対して、ナポレオンはロシアへの遠征を始めました。
ロシア遠征とナポレオンの没落
1812年にモスクワ遠征を行い、40万人の大軍を派遣しました。しかし、冬将軍などに悩まされたナポレオン軍は陸上戦での敗戦を味わいます。
この敗北で弱体化したナポレオン軍は、1813年にライプツィヒの戦い(諸国民の戦い)でプロイセン、オーストリア、ロシア、スウェーデンの連合軍に敗北、エルバ島に流刑となります。

しかし、ナポレオンはエルバ島を脱出し、パリに戻って皇帝へと返り咲きました。ですが、ワーテルローの戦いでイギリス軍に敗北し、ナポレオン戦争は終結しました。
ナポレオン戦争の結果:ウィーン体制・ドイツ関税同盟

ウィーン会議による終戦
ロシア遠を失敗しナポレオンは没落します。1815年にウィーン会議で終結に向かいウィーン体制が成立します。
ウィーン体制とは、ナポレオン戦争後のヨーロッパ秩序の安定のために開催されたウィーン会議で決定された国際秩序で、フランス革命とナポレオン戦争以前の秩序を復活させた体制のことです。
これを契機にドイツは35の君主国と4つの自由都市から構成されるドイツ連邦が成立します。プロセイン王国やオーストリア王国など様々な国がドイツ連邦に包摂する形になりました。

ドイツ関税同盟の成立とドイツ経済の統合へ
この混乱の中で、ドイツ関税同盟が経済の面からドイツを統合する動きが起こりました。当団体は、バラバラのプロセインの経済を制度的にまとめました。
さらに、1835年に南ドイツ・バイエルン王国のニュルンベルク=フュルト間にドイツ初の鉄道路線が開通しました。こうした鉄道業の登場は関税同盟圏の重工業の発達に巨大なインパクトを与えました。
このようにドイツ圏の関税同盟による経済的な統一が背景にあったことが、第二次産業革命の経済的地盤を用意したのです。
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!西洋経済史に関する理解は深まったでしょうか?他にも西洋経済史の記事は以下にまとめてあるのでぜひ読んでみてください。
また最後におすすめの書籍を紹介したいと思います。まず、この記事は以下の書籍をもとに執筆しています。有斐閣アルマの「西洋経済史」は非常にベーシックな内容となっているので、学ぶ上で非常にためになると思います。
ただ難易度がやや高いので、もう少し難易度を下げたい方は以下の書籍もおすすめです。この「やり直す経済史」は日本に関しても言及しているので、親近感を持って経済史にのぞむことができます。
また、これまでの経済史は西洋中心の考え方になっています。しかし、世界にはアジアやイスラーム地域に関しては忘れられがちです。そこで「グローバル経済史入門」は、東南アジアなども含めたグローバルな経済史を描き出しており、非常に学びが深いです。ぜひ読んでみてください。