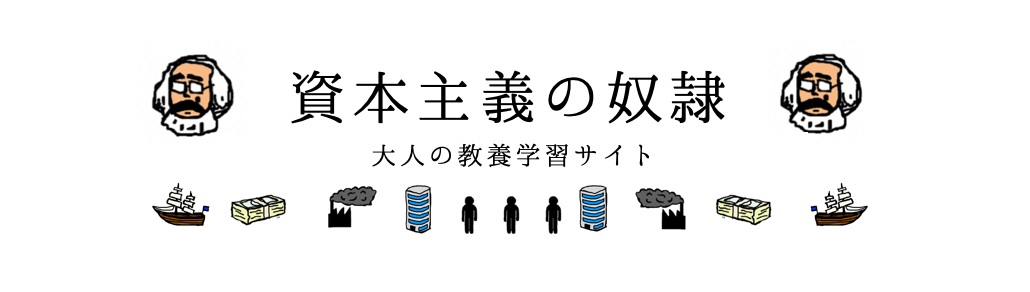この記事では、デヴィッドリカードについて解説します。
彼は、現在の自由貿易論にも多大な影響を与え続けていると同時に、古典派経済学を完成させた人物です。
経済思想について興味がある方は、50人もの経済学者について1人5分で理解きる『世界の経済学 50の名著』はオススメです。
- リカードへの理解が深まる
- 自由貿易の根本的な考え方が身につく
- 労働者がなぜ働き続けなければならないのかがわかる
また他の経済学者にも興味がある場合は以下の記事も参考にどうぞ!
□経済思想まとめ記事
▼古典派経済学
・アダム=スミス
・デイヴィッド=リカード
▼新古典派経済学
・限界革命トリオ
・アルフレッド=マーシャル
▼マルクス経済学
・マルクス
▼ケインズ経済学
・ジョン=メイナード=ケインズ
▼新自由主義
・ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス
・ハイエク
・ミルトン=フリードマン
デヴィッド・リカードとは?

デヴィッド・リカードは、イギリスの経済学者で『経済学および課税の原理』という著作で有名な人物です。

彼は、アダムスミスの理論を精緻化し、古典派経済学の基礎を完成させた人物と言われています。

アダムスミスに関して知りたい方は以下の記事も合わせて読んでみてください。
彼は、1772年にロンドンで生まれました。両親はアムステルダムから移住してきたポルトガル系のユダヤ人です。

彼は成人するとユダヤ人ではない妻を娶り父から絶縁されてしまいます(当時ユダヤ教徒は異教徒と結婚することを禁止されていた)。
そこで、リカードは借金を元手に株式仲介業をはじめ20歳半ばに財産家となりました。現在でいうところのウォーレンバフェットに当たるような人物といっても良いでしょう。
リカードが経済学に興味をもつようになったのは、1799年にアダム・スミスの『国富論』を手にしたことがきっかけであると言われています。
1809年には、当時の地金の高価格と為替の下落の原因をめぐって争われた地金論争に関する論文を『モーニング・クロニクル』に発表して経済時論家としてデビューします。
また、当時論争となっていた穀物法について、賛成派のマルサスとリカードは論争を続けていました。こうした中で、穀物法反対の論理を磨くために、経済学の研究を深めました。

その結果、1817年に『経済学および課税の原理』を公刊します。この著作は『国富論』に次ぐイギリス古典派経済学の代表作となりました。※写真は和訳した書籍
『経済学および課税の原理』により経済学者としての名声を得たリカードは、1819年に下院議員となっています。政治家として、彼は経済・金融問題に大きな貢献を果たし、小さな政府、減税、言論の自由を訴えました。
しかし、1823年に彼は去る事となりました。
リカードの思想の前提:『経済学および課税の原理』

リカードは、『経済学および課税の原理』においてアダムスミスの思想を土台にして、経済の仕組みに関して包括的論理を展開しました。
また、同書はリカードは経済学をより科学的な学問にすることを志向していたため、理論的な表現に徹しています。こうした傾向はスミスとは逆の傾向でした。
そこで同書について解説する前に、リカードの思想の前提とも言える
- 労働価値説
- 経済の捉え方
について解説していきます。
経済の捉え方
まずは、リカードが経済をどのように捉えていたのかについて解説していきます。彼は、資本・土地・労働の3つの要素よって生産物が生み出されるという前提に立っておりました。
例えば、農産物は、
- 小麦を植える土地
- 農機具などの資本
- 農機具を使用して農産物を作る労働
によって生産されています。

また、土地、資本、労働はそれぞれ、土地所有者、資本家、労働者が所有しているとします。
ちなみに彼らは、所有している生産手段から利益を受け取ります。土地所有者であれば地代、資本家は利潤、労働者は賃金をです。

ここで、重要なのは、リカードは土地所有者も資本家も労働者も受け取る利益は平等ではないことを主張しています。この理由について『経済学および課税の原理』でリカードは説明しています(のちの節で解説します)。
リカードの生産物の価値の捉え方:投下労働価値説
リカードはアダムスミスの労働価値説を引き継ぎ理論を展開しました。
厳密にはスミスは支配労働価値説と投下労働価値説の2つを展開し、その中で支配労働価値説を斥ぞけ、投下労働価値説を採用しました(ややこしいので支配労働価値説については解説しません)。
投下労働価値説とは、モノの価値は、生産のために投下された労働量によって決まるという考え方です。
例えば、1枚のTシャツの価値は、その生産のために投下された人間の労働量と同じなのです。

投下労働価値説とは、モノの価値は、生産のために投下された労働量によって決まるということ
投下労働価値説は、のちに古典派経済学に対して大きな変化をもたらすカール・マルクスが受け継ぐことになります。
しかし、リカードは投下労働価値説をのちに修正しています。なぜなら資本蓄積が起こった場合の事を投下労働価値説は説明できないからです。
そこで、モノの価値は、投入した労働と機械などの資本を反映したものという見解をリカードは後に示しています。
Tシャツも労働だけでなく、工場施設や機械も投下されることで生産される事を考えれば当然ですね。

では、リカードの思想の基礎的な部分について抑えた上で、『経済学および課税の原理』の内容について具体的に解説していきます。
のちのリカードの価値の捉え方
モノの価値は、投入した労働と機械などの資本を反映したものという見解をリカードは後に示しています。
収穫逓減の法則
リカードの思想の前提として、収穫逓減の法則があります。
収穫逓減の法則とは、1つの土地からの収穫量は、投入した労働量の増大に比例せず、労働者を増やしていくたびに得られる収穫量は逓減していくという法則です
そのため、収穫量をさらに増加させるためには、肥沃度が低くて生産性の低い土地を利用する必要性があります。
収穫逓減の法則は、後ほど説明する差額地代論の前提となっていきます。ちなみに同時期にマルサスも収穫逓減の法則を発見していたと言われています。

収穫逓減の原則:1つの土地からの収穫量は、投入した労働量の増大に比例せず、労働者を増やしていくたびに得られる収穫量は逓減していくという法則
価値分配論:経済の富はどのように分配されるのか

リカードは、社会で生み出された価値はどのように土地所有者、労働者、資本家に分配されるのかを明らかにしました。
以下ではこの点について解説していきます。
賃金生存説と自然価格:労働者への分配
まずは、労働者にはどのように社会の富は分配されるのでしょうか?それは賃金という形で分配されます。
リカードは、労働者の賃金は、単なる生存維持のために必要な生活費(生産費)を基準に決められると言っています。これを賃金生存説と言います。
一時的に賃金が上がっても、最終的に生産費と同じ程度の賃金に戻ってしまうのです。
賃金生存説:労働者の賃金は、単なる生存維持のために必要な生活費(生産費)を基準に決められる
結果として資本家や土地所有者のようなお金持ちと、労働者のような貧乏人の階層が社会に根付いてしまうのです。
しかし、なぜ労働者は生産費ギリギリの賃金に戻ってしまうのでしょうか?それは、労働の市場価格は常に自然価値に収斂していくからです。
詳しく解説していきます。商品には
- 市場価格
- 自然価格
があります。自然価格とは投入した労働と機械などの資本を反映した価格のことです。
一方で、市場価格とは需要と供給のバランスが崩れてしまい自然価格と乖離した価格のことです。また、市場価格は常に自然価格に収斂していくという前提があります。
例えば、自然価格よりも高い商品があったとします。しかし、高い価格は利潤を多くもたらします。こうした商品は競合が多くなってしまい、供給過多になってしまいます。

結果として市場価格は自然価格に収斂していくのです。
- 自然価格:投入した労働と機械などの資本を反映した価格のことです。
- 市場価格:需要と供給のバランスが崩れてしまい自然価格と乖離した価格のこと
リカードは、この自然価格と市場価格の原則が労働にも適用されると考えました。
労働力が不足していたとします。その場合、労働者は高賃金を要求できます。
しかし、高賃金になると労働者は豊かになります。すると労働人口が増加し、労働の供給が多くなってしまうのです。結果として、労働価格は自然価格まで下がることになります。

資本家は労働者の生活費を抑えることで賃金を抑える事ができます。そこで、資本家は食物や生活必需品の価格を低く抑える事が重要になります。
収穫逓減の法則と差額地代説:土地所有者への分配
では続いて、土地所有者の富の分配法則について解説します。
土地所有者は地代によって富を得ます。地代は生産者(資本家)の収益から巻き上げます。また、生産者は収益を得るために労働者を投入して生産を行います。

では地代はどのような水準で決定されるのでしょうか。それは、リカードが生み出した差額地代論という考え方から説明できます。
農地の地代水準は、その土地が肥沃さによって決まります。
その際に、最劣等地で投下された労働量によって穀物の価値が基準となり、その価値を上回る優良地の産出分は土地所有者が得ることになるというのが差額地代論と言います。
式で表すと以下のようになります。
その土地で生産した時の収益 – 最劣等地の収益 = 土地代
なぜそうなるのでしょうか?
差額地代論:最劣等地で投下された労働量によって穀物の価値が基準となり、その価値を上回る優良地の産出分は土地所有者が得ることになるというのが
その土地で生産した時の収益 – 最劣等地の収益 = 土地代
劣等地では、多くの生産物を生産できません。そのため、この土地の生産物は高価格になります。
一方で優良地では、1つの土地で多く生産することができます。そのため、安い価格で販売が可能です。しかし、この土地の生産者は最劣等地の高い価格に合わせようとします。
なぜなら、市場で高い農産物が出回っているのをみて、より利潤を得るために一番高い価格に合わせようとするからです。
この時、土地所有者はその土地で生産した時の収益 から最劣等地の収益を差し引いた分を地代として徴収しようとするのです。
利潤理論:資本家への分配
リカードは、事業主(資本家)が労働者に賃金を支払い、土地所有者に地代を払った後に残るものが資本家の利潤となるとしています。

また、その際に、利潤率はどの産業でも一定の水準にあると考えていました。
なぜならある産業の利潤率が高い事がわかれば、他の産業からすぐに資本が流入してくるからです。結果生産量が増えて、価格が下がり利潤が減少することになります。これは逆もまた然りです。
結果として利潤率はどの産業でも一定になるのです。
利潤率はどの産業でも一定になる
比較優位の原理:自由貿易の理論の根拠

リカードは、自由貿易論者であることは先に述べたとおりです。
彼は、当時の重商主義的に他国を犠牲にして、自国を豊かにするという考えを真っ向から否定しています。
彼は、貿易する国々はお互いに共存が可能であり、一斉に成長することが可能であると考えました。そこで彼の自由貿易論
絶対優位
彼は、比較優位の原理を根拠に自由貿易論を展開しました。それが比較優位の原理です。この原理を理解するためんには、絶対優位について抑えておく必要性があります。
絶対優位とはある国がべつの国に比べて効率的に財を生産でき、他の国に比べて労働力や資本を投下しなくても効率よく利益が獲得できる状態のことです。
例えば、ポットと船舶の財と、イギリスとフランスしかない経済を想定してください。
その際に
- イギリスはポットと船舶両方の生産をコスパよくできる
- フランスはどちらも微妙という例です。
そのため、輸出の際にイギリスがすべての財の覇権を握るだろうという考えです。これが絶対優位になります。

絶対優位:ある国がべつの国に比べて効率的に財を生産でき、他の国に比べて労働力や資本を投下しなくても効率よく利益が獲得できる状態
比較優位の原理
比較優位とは、ある一定の状況下において相対的に、生産が得意な財がある状態のことを指します。
そこで、比較優位の原理とは、それぞれ相対的に生産が得意な財が存在するから、自国で生産しないものは貿易で賄って得意な方に注力すればよいという考えです。
ちなみにここではいう生産が得意とは、費用をかけずに生産ができるということです。
絶対優位ですと、どちらかの国が覇権を握る身も蓋もない状況でした。それが、比較優位の原理ですと、2国で分担して生産、輸出をすることができます。これにより全体として効率的な生産が可能となるのです。
- 比較優位:ある一定の状況下において相対的に、生産が得意な財がある状態のことを指します。
- 比較優位の原理:それぞれ相対的に生産が得意な財が存在するから、自国で生産しないものは貿易で賄って得意な方に注力すればよいという考えです。
実際に事例を見ていきましょう。2国2財の経済を想定します。
比較優位の例
イギリス:2財どちらも生産が得意な国
- 船舶の生産に関してかなり得意(生産力4)
- ポットの生産に関してやや得意(生産力3.5)
フランス:2財どちらの生産も微妙な国
- 船舶の生産に関してはかなり不得意(生産力1)
- ポットの生産に関してやや不得意(生産力3)
フランス国内ではポットの生産が相対的に得意です。これが、フランスはイギリスに比べてポットの生産において比較優位にあるということになります。

一方で、イギリスは船舶の生産においてフランスに比較優位にあると言えます。そこで、それぞれ得意な方の財の生産に特化して、足りない財は貿易で賄えば2国間で効率的に財を生産することができるのです。
比較優位説の問題点
比較優位の原理に関しては、問題点があります。
比較優位の原理は国内政策や国際政治を考慮しないならば、大きな役に立ちます。しかし、現実には、全く優位ではない産業でも生産を続けている国はあります。
その国が自国の産業を保護するために、国際政治に歪みが生じてしまうのです。こうした政策をとるのは先進国だけでなく、発展途上国が保護政策をとることもあります。
輸入を国産品に代替するために、工業化政策をとることで、雇用と産業を創出し経済成長を果たした例もあります。
必ずしも比較優位の原理を適用できる場面は多くありません。
さいごに

ここまで、リカードの思想について説明してきました。
さらに詳しく学びたい方は、これから紹介する書籍を読むことでさらにマルクスへの理解を深めることができると思います。
まず紹介するのは、「資本論 (まんが学術文庫)」です。何回なマルクスの『資本論』を漫画でわかりやすく理解することができます。
また、経済思想について興味がある方は、50人もの経済学者について1人5分で理解きる『世界の経済学 50の名著』はオススメです。