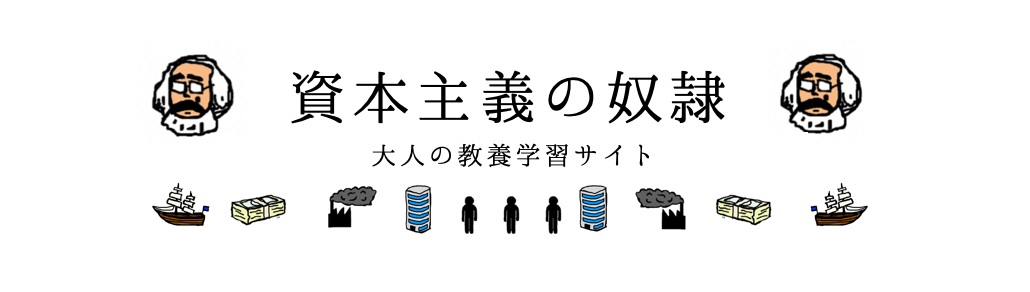この記事ではマクロ経済学の全体像について触れていきます。
また、オススメの書籍もおいておくので是非合わせてお読みください。
マクロ経済学の全体像がつかめる
経済学とは?
マクロ経済学の全体像
→ミクロ経済学はコチラ
▼財市場シリーズ
① 国民所得・三面等価の原則
② 有効需要の原理・需給均衡式
③ 均衡国民所得・乗数効果
④ 45度線分析・インフレーションギャップ
▼労働市場シリーズ
・AD-AS分析
・IS-LM分析
▼貨幣-債券市場シリーズ
・貨幣需要・貨幣供給
▼その他
・経済成長理論
・国際マクロ経済学
マクロ経済学とは?

マクロ経済学とはなんなのか?この節で解説していきます。
マクロ経済学とは?
マクロ経済学とは、国を単位として経済全体を分析する学問です。つまり、国全体が今どうなっているのかを分析するのです。そのため、一つの商品や個人、一企業などは分析の対象になりません。
また、この学問の目的は、国内の人々の生活を良くするはどうするかを考えることです。この国内の人々の生活を良くするとは、完全雇用の状態を実現する事です。
完全雇用とは、労働の意思と能力のある者がすべて働いている状態のことです。
マクロ経済学
- 国を単位として経済全体を分析する学問
- 完全雇用を実現する事を目的としている
マクロ経済学の始まり
マクロ経済学の始祖と言われるのはジョン・メイナードケインズです。

始まりは1929年の世界恐慌までさかのぼります。世界恐慌では、大量の倒産や失業が発生しました。

この恐慌までは、アダムスミスを始祖とする古典派経済学(現在のミクロ経済学)が力を持っていました。しかし、古典派経済学は不況に対して有効な処方箋を出すことができませんでした。
なぜなら、古典派経済学は自由放任主義という考えを持っていたため、恐慌があっても放置しておくべきという考えだったからです。
そこで、恐慌に対処すべくジョン・メイナード・ケインズという経済学者がケインズ経済学という潮流を作り出しました。

そして、完全雇用を実現するために必要な理論を構築したのです。
彼は、政府がゴリゴリ経済に手を出す事で完全雇用を実現できると主張します。ケインズ経済学は様々な国で取り入れられました。
このケインズ経済学がのちのマクロ経済学へと繋がっていきました。
マクロ経済とは?
では、そもそもマクロ経済学は経済をどのように捉えるのでしょうか?
まず、国の中でモノ・ヒト・カネがぐるぐると循環していると考えます。これらは、マクロ経済学の3つの市場に該当します。それが以下のようになります
- モノ→財市場
- ヒト→労働市場
- カネ→貨幣-債券市場
これらの市場の詳細は後ほど取り扱いますが、とりあえず労働市場はヒトを、財市場はモノを、債券-貨幣市場はカネを取り扱う市場だと理解しておきましょう。

マクロ経済学は、経済をヒト・モノ・カネを国の中をぐるぐる循環しているととらえます。
そして、それぞれ
- モノ→財市場
- ヒト→労働市場
- カネ→貨幣-債券市場
の三つの市場に該当します。
財市場

まず、財市場を取り扱っていきます。先に述べたように、財市場はモノを取り扱う市場です。財市場の状況を知る上で、重要なのが国内総生産(GDP)という指標です。これにより景気の良し悪しを図ることができます。
国民所得
をまとめて国の経済の状態を図る指標には
- 国民所得:NI
- 国内総生産:GDP
- 国内純生産:NDP
などがあります。
ここでは、国内総生産(GDP)について説明していきます。GDP(国内総生産) とは一定期間に生み出された付加価値の合計です。GはGross(総)の略、DはDomestic(国内)、PはProduct(生産)の略になります。

また、付加価値とは企業により生み出された製品・サービスなどの価値の中で、企業の活動によって生み出された価値のことを指します。
付加価値:企業により生み出された財・サービスの価値の中で、企業自身の活動によって生み出された価値のこと
例えば、鉄を作る会社Aと、鉄を分割して車の部品にする会社B、車を組み立てる会社Cがあったとします。その際に、B社がA社から仕入れる原材料や、C社がB社が原材料として仕入れる鉄や部品などは付加価値ではありません。これは中間生産物と言います。
あくまで、企業やその労働力の活動によって生み出された部分が付加価値になるのです(下記の図の赤い部分)。

ここから、国内総生産(GDP)は、
GDP(国内総生産)=総生産額-中間生産物
と言い表すこともできます。
GDP(国内総生産) :一定期間に生み出された付加価値の合計
三面等価の原則
三面等価の原則とは、国内総生産(GDP)や国民所得(NI)が生産面、支出面、分配面の三つの側面が常に等しいとう原則のことです。

三面等価の原則を計算式で表すと、
Y【生産面】
= C(消費)+I(投資)+G(政府支出)+(X(輸出)-M(輸入))【支出面】
= C(消費)+S(貯蓄)+T(税金)【分配面】
というように表すことができます。このように、GDPは様々な要素、例えば消費や投資などによって決定されることがわかると思います。
三面等価の原則:国内総生産(GDP)や国民所得(NI)が生産面、支出面、分配面の三つの側面が常に等しいとう原則。
有効需要の原理:需給均衡式
需要とは欲しいと人が思うことを指します。つまり、実際に購入したかどうかは関係ありません。
一方で、マクロ経済学のいう有効需要とは金銭的な裏づけがある需要のことです必要です。ミクロ経済学で言われる需要とは違うという点は抑えておきましょう。

有効需要の原理とは、経済活動(供給)の水準は有効需要によって決まるという事です。
つまり、有効需要が多ければ多いほど企業は生産を増やしていくという事です。そして有効需要の大きさが国民所得の大きさを決めるのです。

この有効需要が、最終的に国民所得を決定するとするのがケインズの主張でした。
有効需要の原理:経済活動(供給)の水準は有効需要によって決まる
需給均衡式
有効需要の原理は需要が供給を決定するという考えでした。これを式で表したものが需給均衡式です。Cは消費、Iは投資です。そして、Yは国民所得もしくはGDPになります。
消費(C)や投資(I)を増やすことで、国民所得(Y)を増加させることができると考えたのです。

乗数効果
投資などの支出を増加させたることで有効需要が増加します。その際に増加した額より大きく国民所得が拡大することを乗数効果と言います。
より具体的に説明すると
生産者が投資を増やす→国民所得が増加する→消費が増える→国民所得が増える→さらに消費が増える→さらに国民所得が増加する→さらに消費が増える→・・
といったサイクルを経る事で国民所得が当初の投資額の何倍もの効果が国民所得に現れるのです。(以下の図参照)

乗数効果:投資などの支出を増加させたることで有効需要が増加します。その際に増加した額より大きく国民所得が拡大すること
他には、マクロ経済学では財市場の説明において、有効需要、45度線分析などの理論が展開されていきます。
より詳細を知りたい方は以下の記事も読んでみてください。三部構成でかなり重厚な説明となっています。より深めたい方は読んでみてください。
貨幣-債券市場

人はものを交換する時にカネを使います。このカネの取引がおこなわれる市場が貨幣-債券市場です。この節では、貨幣-債券市場について取り扱います。
貨幣-債券市場
貨幣-債券市場とは、カネが取引される市場のことです。カネにも二種類あり
- 貨幣
- 債券
の二つがあります。貨幣とは、現金や預金、債券は国債と社債、株といったものが挙げられます。

カネは、財・サービスの売り買いの際に使用されます。皆さんの生活にも馴染み深いカネの使い方だと思います。これは財市場でのお金の使い方です。
一方で、貨幣-債券市場では、カネを使ってカネを増やすことができます。そこで人々は金でカネを増やすために、貨幣と債券でよりカネが増える方を選択します。

貨幣-債券市場とは、カネが取引される市場のことです。カネにも二種類あり
- 貨幣
- 債券
の二つがあります。貨幣とは、現金や預金、債券は国債と社債、株といったものが挙げらる。
貨幣需要
貨幣需要、つまり貨幣を欲しがることです。の動機として、次の3つがあげられます。
- 取引動機:財の取引に使用するため。
- 予備的動機:将来の不確実な支払に備えるため
- 投機的動機:資産運用のため。
この貨幣需要を考える際に重要なのが流動性選好説です。流動選好説とは、貨幣需要量は利子率のと反比例するという考え方です。わかりにくいのでもう少し詳しく説明します。
すぐに消費として使える度合いのことを流動性といいます。貨幣はすぐにモノと交換ができますが、債券は使うことができません。貨幣は流動性が高く、債券は流動性が低いということになります。

債券で持つ場合は貨幣のメリットであるすぐ使えるということを犠牲にすることになります。その代わりに得られるのが利子となります。
そのため、人々が資産を貨幣でもつか、債権や株式でもつかは利子率で決まるのです。
- 貨幣需要、つまり貨幣を欲しがること。貨幣を欲しがる動機には以下のものが挙げられます。
- 取引動機:財の取引に使用するため。
- 予備的動機:将来の不確実な支払に備えるため
- 投機的動機:資産運用のため。
- 人々が資産を貨幣でもつか、債権や株式でもつかは利子率で決まる
貨幣供給
貨幣供給とは、 市場に流通している通貨の量のことです。
貨幣供給は主に中央銀行が担っています。中央銀行は、金融システムの頂点にある存在で、貨幣を自由に作ることができます。しかし、これだけでは、貨幣供給は収まりません。
そこで重要なのが、信用創造です。信用創造とは銀行が貸し付けによって預金通貨を創造できる仕組みの事を指します。
人々は銀行に預金をします。そして、銀行は預金を様々な企業などに貸し出します。そうすると、企業は資金を元に利益を得ることができます。
そこで生まれたお金はさらに別の銀行に預金されることになります。こうした連鎖を無限に繰り返すことで、初めに受け入れた預金の何倍もの派生的預金が、世の中に発生することになります。これが信用創造です。

信用創造により、中央銀行が当初製造したお金の何倍ものお金が市場に出回ることになるのです。
- 貨幣供給: 市場に流通している通貨の量のことです。
- 信用創造:銀行が貸し付けによって預金通貨を創造できる仕組みの事。これにより貨幣供給が実現している
IS-LM分析

マクロ経済学とは、ある国の経済を全体的に分析する学問でした。
これを利用して政府は経済政策を行うのでした。その中で、IS-LM分析という手法は経済政策の効果を図ることに役立ちます。
IS-LM分析とは?
IS-ML分析は、経済政策の効果を図る上で役に立ちます。しかし、ISやMLとは何を示しているのでしょうか?分解して解説します。
- Iは投資(Investment)
- Sは貯蓄(Saving)
- Lは貨幣需要(Liquidity)
- Mは貨幣供給(Money Supply)
を意味します。

まずは、ISの側面を説明します。貯蓄(Saving)とは供給に当たります。貯蓄(S)とは預金をすることを指します。そして、この預金は投資(I)などに回されます。ちなみに、タンス預金などは経済学では貯蓄(S)とはいいません。
この貯蓄(S)を元に、投資(Investment)が行われ企業は生産を行います。この投資(I)と貯蓄(S)が一致するところで財市場が均衡します。これをグラフで表したのがIS曲線です。
LMにおいて、Lは貨幣需要(Liquidity)でMは貨幣供給(Money Supply)のことを指します。ここで、貨幣需要(L)と貨幣供給(M)が一致するとき、貨幣市場が均衡します。これをグラフで表したのがLM曲線です。
また、X軸は国内総生産(Y)、縦軸は、利子率(r)となっております。

IS-ML分析は、経済政策の効果を図る上で役に立ちます。しかし、ISやMLとは何を示しているのでしょうか?分解して解説します。
- Iは投資(Investment)
- Sは貯蓄(Saving)
- Lは貨幣需要(Liquidity)
- Mは貨幣供給(Money Supply)
を意味します。
国民所得と利子率
IS曲線とLM曲線は、それぞれの市場が均衡すると国内総生産(Y)と利子率(r)のくみあわせを示しております。
国内総生産(Y)は、財市場で決まる値ですが貨幣市場にも影響を与えます。また、利子率(r)は貨幣市場で決まる値ですが、財市場にも影響を与えます。

そのため、国内総生産(Y)と利子率(r)を考えることで、貨幣市場と財市場の関係性を理解することができます。
IS曲線とLM曲線が交わる点は、財市場と貨幣市場が同時に均衡する国民所得と利子率の組み合わせになります。この状態が経済としてはとても効率的な状態になります。

- IS曲線とLM曲線は、それぞれの市場が均衡すると国内総生産(Y)と利子率(r)のくみあわせを示しております。
- 国内総生産(Y)と利子率(r)を考えることで貨幣市場と財市場の関係性を理解することができます。
労働市場

モノを作るためにヒトが働く必要があります。そのため、労働力は市場で商品として取引されます。この労働力の市場のことを労働市場といいます。
労働市場において
- 賃金
- 物価
- 失業率
の三つが重要なキーワードになります。

賃金・賃金率
労働の対価として支払われるのは賃金(W:Wage)です。つまり賃金率です。賃金率(W)を見れば経済の状態がわかるといわれています。
景気がいい時には、労働需要が増加して人手が不足するので賃金率(W)は上昇します。一方で、景気が悪い時には労働需要が減少し、人手が余るので賃金率は減少します。
物価
また、賃金が高いのか低いのかは、物価が高いのか低いのかを考慮する必要性があります。インフレーションやデフレーションなどというように、物価は変動します。
昔の100円は非常に価値が高かったですが、現在ではそこまで価値は高くないことからもわかると思います。
失業率
失業率は、労働力人口のなかで失業者が占める割合のことです。計算式は以下のようになります。もちろん先に書いたように、ここでの労働力も雇用者と失業者の合計となります。
失業率=失業者数/労働力人口×100
=失業者数/(雇用数+失業者数)×100
景気が良い時にはもちろん失業率が下がります。また、景気が悪い時には失業率が上がります。
労働の対価として支払われるのは賃金(W:Wage)です。つまり賃金率です。賃金率(W)を見れば経済の状態がわかるといわれています。
AD-AS分析
続いて、IS-LM分析を先に解説しました。財政政策や金融政策を発動することで、国民所得や利子率がどのように変化するのかを見ることができました。これにより経済政策の効果を測定することができました。
これを労働市場にまで分析ができるように発展させたものがAD-AS分析になります。財市場における物価と国民所得の組み合わせを表したAD曲線(そう需要曲線)と、労働市場における物価と国民所得の組み合わせを表したものになります。
AS曲線は右下がりです。

AD曲線は、ケインズ派と古典派で違います。ケインズ派は右上がりで、古典派は垂直だと考えました


こうした、AS-AD分析に関する内容は以下の記事でより詳しく書いているので是非読んでみてください。
IS-LM分析を発展させることで、金融政策や財政政策の影響を労働市場における国民所得や物価状況を分析できる手法。
経済成長論とは?

僕たちは、とても豊かな生活を送っています。コンビニで肉とご飯がたくさん入った弁当を食べ、毎年インフルエンザのワクチンを摂取して、綺麗な水を飲むことができています。…
しかし、ひと昔前には、伝染病は流行り早死にしたり、ご飯もろくに食べれないというのは当たり前でした。こうした生活水準の改善は、経済成長の成果によるものです。
マクロ経済学では、この経済成長を体系的かつ論理的に分析する手法が確立しています。
2つの経済成長率:保証成長率・自然成長率
経済成長を考える上で、最適成長を考える必要があります。最適成長の目安は、国民所得の変化の割合である経済成長率で測られます。
この経済成長率には
- 保証成長率(Gw:warranted rate of growth)
- 自然成長率(Gn:natural rate of growth)
があります。最適成長とは、
- 保証成長率(Gw)と自然成長率Gn)が一致している状態
- 財市場と労働市場が均衡している状態
が達成されている状態のことです。

この時、財市場が均衡しているときの経済成長率を保証成長率(Gw)と言います。
一方で、労働市場において完全雇用が達成されているときの経済成長率を自然成長率(Gn)と言います。完全雇用とは、失業者(厳密には非自発失業者)が存在しないことを指します。
- 保証成長率(Gw):財市場が均衡しているときの経済成長率
- 自然成長率(Gn):労働市場において完全雇用が達成されているときの経済成長率
国民所得は資本と労働の組み合わせ:生産関数
企業は、資本と労働を組み合わせて財を生産します。これにより国民所得が生み出されます。

この2つの生産要素の組合せをしめしたものが、生産関数です。生産関数とは、生産要素(労働・資本)の投入量と、投入の結果えられる生産量の関係をあらわしたもののことです。
資本
国民所得(Y)は、資本(K)と労働(L)によって生産されます。資本(K)と国民所得(Y)の比率は、資本係数(v)であらわします。
資本係数(v)とは、生産量1単位を生産するのに必要な資本(K)を示します。資本係数から、その国の経済の生産の仕組みがわかります。

これを式であらわすと次の形になります。
資本係数(v)=資本(K)/国民所得(Y)
労働力
労働(L)と国民所得(Y)の比率は、労働者1人当たりの国民所得(y)であらわします。この指標は、労働生産性といって、その国の労働者が生み出す価値を見ることができます

式であらわすと次の形になります。
労働者1人当たりの国民所得(y)=国民所得(Y)/労働力(L)
- 資本係数(v):資本(K)と国民所得(Y)の比率
- 労働者1人当たりの国民所得(y):労働(L)と国民所得(Y)の比率は、
国際マクロ経済学について

この記事では、国際マクロ経済学の概要を説明します。詳細は以下の記事で解説しているので合わせてお読みください。
国際マクロ経済学とは?
国際マクロ経済学とは、海外との経済関係を分析の対象としてマクロ経済の理論を応用して経済を分析する経済学の一分野のことです。ここではマクロ経済の全体像を見てみましょう。
海外との関係を考慮したマクロ経済には
- 国際収支
- 為替レート
と言う要素が付け加わります。
国と国はカネやモノを取引します。その際に儲かったり(黒字)、逆に儲からなかったり(赤字)します。これを国際収支と言います(後ほど詳しく解説します)。

一方で、海外と取引をする際には相手国の通貨と自国の通貨という複数の通貨基準を考える必要があります。この時、相手国と自国の通貨の交換比率を為替レートと言います。
為替レートによっては、前より安く他国の商品を変えたり、もしくは逆のパターンがあります。またこの為替レートを支えているのが為替相場という制度になります。

為替レートと国際収支はお互い相互に影響を与え合う関係にあり、これらの関係は国内のマクロ経済にも影響を与えます。
以下では、国際収支、為替レートについて解説します。
- 国際収支:その国の儲かったり(黒字)、逆に儲からなかったりする(赤字)部分
- 為替レート:相手国と自国の通貨の交換比率
国際収支とは?
一定期間内の一国全体の対外的な経済取引をまとめたものを国際収支(BP:balance of payments)といいます。この国際収支は2つにわけることができます。それが
- 経常収支(current balance)
- 資本収支(balance of capital account)
財やモノの取引によって生まれるモノが経常収支(current balance)です。資産や負債などのカネそのものやりとりが資本収支(balance of capital account)です。

この経常収支と資本収支の2つを合計したものが国際収支になります。
国際収支 = 経常収支 + 資本収支
この2つの収支は、まずは望ましい状況として国際収支が均衡している状態を考えます。実際には黒字になったり、赤字になったりします。
国際収支の均衡は経常収支と資本収支の合計が、プラス・マイナス・ゼロの状態を示します。
経常収支+資本収支=0
・経常収支(current balance):財やモノの取引によって生まれるモノが
・資本収支(balance of capital account):資産や負債などのカネそのものやりとりが
・経常収支と資本収支の2つを合計したものが国際収支
・経常収支と資本収支がプラマイゼロの時に国際収支は均衡する
為替レートとは?
ある国と相手国の貨幣の交換比率を、為替レート(exchange rate:為替相場)といいます。
為替レートは
- 1ドル=○円
- 1元=○円
とあらわされます。これを自国通貨建て為替レートといいます。では為替レートとは何か?日本円とアメリカドルを例に見てみましょう。

1ドル=80円が1ドル=100円となった場合は円安になります。アメリカの1ドルで80円のものしか買えませんでした。しかし、1ドルで100円の日本の商品を変えるようになります。
円安とは円の価値がドルに比べて下がっていることを指します。この価値が下がっていることを円安(減価)と言います。
これらの現象をまとめて為替レートが上昇すると言います。
1ドル=100円が1ドル=80円となった場合は円高になります。1ドルで100円のものを買えたのに、1ドル=80円になることで、80円のものしか買えなくなります。
円高とは、円の価値がドルに比べて上がったことを指します。価値が上がることを円高(増価)といいます。
この現象をまとめて為替レートが下降したと表現されます。

- 円安とは円の価値がドルに比べて下がっていること
- 円高とは、円の価値がドルに比べて上がったこと
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事をきっかけで少し経済学について理解を深めたいと思った方は、以下の書籍から初めてみるのがおすすめです!
それは、『スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ミクロ編・マクロ編』です。
こちらはミクロ経済学に関して難しい数式を使うことなくわかりやすく説明してくれています。
これらの本を理解できたら、次に『スティグリッツ入門経済学』を読んでみるのもアリだと思います。ですが、正直、信じられないくらい分厚いので覚悟は必要かもしれません。
しかし、この本を読めば経済学という学問の全体像を知ることができるのでオススメです。