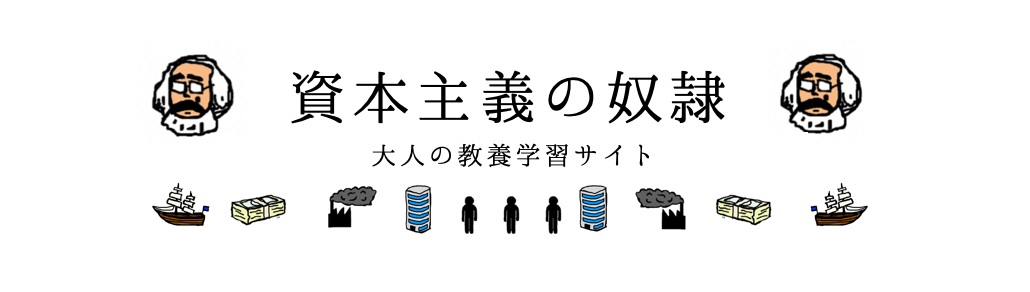この記事では、有効需要の原則と需給均衡式について解説していきます。三面等価の原則で言うところの支出の部分を主に取り扱うことになります。

- マクロ経済学の全体像がつかめる
- 財市場の概要をつかめる
- 有効需要の原理とは?
また、この記事はマクロ経済学の基礎的な部分を理解していた方が読みやすいと思います。興味のある方は以下の記事も合わせて読んでみてください。
経済学とは?
マクロ経済学の全体像
▼財市場シリーズ
① 国民所得・三面等価の原則
② 有効需要の原理・需給均衡式
③ 乗数効果
④ 均衡国民所得
⑤ 45度線分析・インフレーションギャップ
▼労働市場シリーズ
・AD-AS分析
・IS-LM分析
▼貨幣-債券市場シリーズ
・貨幣需要・貨幣供給
▼その他
・経済成長理論
・国際マクロ経済学
有効需要の原理とは?

この節では、有効需要の原理について解説をしていきます。有効需要の原理は、マクロ経済学において非常に重要な原理になるので必ず抑えておきましょう。
有効需要とは
需要とは欲しいと人が思うことを指します。つまり、実際に購入したかどうかは関係ありません。
一方で、マクロ経済学のいう有効需要とは金銭的な裏づけがある需要のことです必要です。ミクロ経済学で言われる需要とは違うという点は抑えておきましょう。

マクロ経済学において有効需要は、経済を良い方向にする上で非常に重要視されています。
有効需要の原理とは
有効需要の原理とは、経済活動(供給)の水準は有効需要によって決まるという事です。
つまり、有効需要が多ければ多いほど企業は生産を増やしていくという事です。そして有効需要の大きさが国民所得の大きさを決めるのです。

有効需要の原理:経済活動(供給)の水準は有効需要によって決まる
需給均衡式とは?

先ほど説明した有効需要と供給の関係性を示したものが需給均衡式です。需給均衡式は以下のように示されます。

需給均衡式:有効需要と供給の関係性を示したもの
先に述べたように総供給はY(生産:Yield)で表します。企業などが生産した付加価値のことを指します。
総需要(有効需要)は、C(消費)とI(投資)を合計したものです。
消費(C)とは、私たちが普段行なっている購買行動のことを指します。一方で、投資(I)とは企業などが利益を拡大させるために工場や建物にお金を払う行為のことを指します。
三面等価の原則より総供給と総需要は等しくなるので、以下のような数式が成り立ちます。
Y=C+I
これを需給均衡式と言います。
さいごに

最後まで読んでいただきありがとうございます!
この記事をきっかけで少し経済学について理解を深めたいと思った方は、以下の書籍から初めてみるのがおすすめです!
それは、『スタンフォード大学で一番人気の経済学入門 ミクロ編・マクロ編』です。
こちらはミクロ経済学に関して難しい数式を使うことなくわかりやすく説明してくれています。
これらの本を理解できたら、次に『スティグリッツ入門経済学』を読んでみるのもアリだと思います。ですが、正直、信じられないくらい分厚いので覚悟は必要かもしれません。
しかし、この本を読めば経済学という学問の全体像を知ることができるのでオススメです。